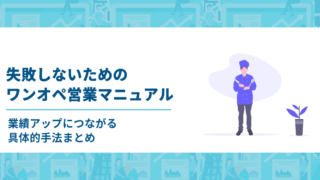1. なぜ今「ワンオペ飲食店」が増えているのか?【時代背景と現実】
人手不足・人件費高騰が常態化している
近年、飲食業界において避けて通れない課題が「人手不足」です。特に都市部では、求人を出しても応募が来ない、採用してもすぐ辞めてしまう、といった声があちこちから聞こえてきます。加えて最低賃金の引き上げにより、アルバイト一人にかかる人件費も年々増加。小規模店舗にとっては、人を雇うということ自体がリスクになりつつあるのです。
このような状況下で注目されているのが、「ワンオペ=一人で店舗を切り盛りする運営スタイル」です。従業員を雇わず、オーナー自身が調理・接客・会計などすべてを担うことで、固定費をぐっと抑えることができます。
特に、開業初期のキャッシュフローが厳しい時期において、人件費をかけないというのは大きなメリットです。飲食店経営のリスクを最小限にしながら挑戦できるモデルとして、ワンオペはますます注目されるようになっています。
ミニマム開業のニーズと「一人で回せる店」への注目
「大きな店舗より、小さく始めて確実に利益を出す」。そんな開業スタイルが、今の時代にフィットしています。
SNSを使えば宣伝も低コストででき、ECでのテイクアウト販売や事前決済の導入など、テクノロジーの進化がワンオペを支える土台になっています。特に20〜30代の若手開業者の中には、最初から「一人でやること」を前提に店舗設計や物件選びを進めるケースが増えてきました。
また、間借り営業やポップアップショップなど、小規模でのトライアルを経てワンオペに移行する流れも加速。低リスク・高回転のモデルが、飲食店開業の新しい常識になりつつあるのです。
ワンオペ成功事例に見るメリット・デメリット
実際にワンオペで成功している店舗には、いくつか共通点があります。
たとえば、都内のある立ち飲みバーでは、カウンター内からすべての業務が完結するような設計を行い、接客の負担を最小限にしています。料理は簡素ながらクオリティの高いおつまみとドリンクの組み合わせに絞り込み、オペレーションも最適化。結果的に月商100万円超を一人で叩き出す店舗となっています。
一方で、デメリットも明確です。まず、体調不良や緊急時に代わりがいないというリスク。そして、精神的・肉体的な負荷がかかりやすく、長期運営を視野に入れると持続可能性に課題があることも。こうした点を理解した上で、事前の仕組みづくりや「限界を超えない設計」が求められます。
2. ワンオペ向け物件の3つの絶対条件【レイアウト・坪数・立地】
① レイアウト|一人で回すための「導線設計」が命
ワンオペ飲食店の物件選びで最も重要なのが、**レイアウト(導線設計)**です。どれだけ立地がよくても、どれだけ安く借りられても、レイアウトが悪ければ、営業中に「無駄な移動」や「客対応の遅れ」が生じてしまいます。
理想は、「厨房とホールをできるだけ一体化」させた設計。カウンター越しにすべてのオペレーションが完結できると、動線のロスを大幅に削減できます。たとえば、
- 調理をしながらお客さまの様子を確認できる
- 注文や会計もカウンター越しで対応可能
- 配膳や片付けも立ち位置を変えずに済む
このような設計であれば、ピークタイムでも一人でスムーズに対応可能です。
また、視認性もポイント。厨房から死角になるテーブル席が多いと、呼ばれても気づけなかったり、トラブルに対処できなかったりします。その意味でも、L字やU字カウンターなど、視界が広く取れる構造が理想的です。
② 坪数|目安は5〜10坪!狭すぎず広すぎない「適正サイズ」
次に意識したいのが「坪数」です。ワンオペ営業では、広すぎる物件は逆に負担になります。目安としては5〜10坪程度がちょうど良いサイズ感。これくらいであれば、
- 客席数が6〜10席程度に収まり、回しやすい
- 家賃や光熱費などの固定費もコンパクト
- スタッフ不在でも目が届く範囲で営業できる
といった利点があります。
一方、3坪以下の超ミニマム物件では厨房が狭すぎたり、トイレの設置が難しかったりと、営業許可やオペレーションに影響が出る可能性があります。また、10坪を超えると清掃や補充作業の時間が増え、「一人で対応するには限界がある」サイズ感になることも。
収益性を上げるには、坪数に見合った回転率の設計も重要です。「少人数・高単価・高回転」を実現することで、狭くても利益が出せる仕組みを整えましょう。
③ 立地|「一人で回せる客数」がポイント
立地を選ぶ際も、「集客数」より「一人で回せるキャパ」を軸に考えることが大切です。
たとえば、駅前の超一等地に出店すれば、確かに集客は見込めます。しかし、来客が多すぎると一人では対応しきれず、サービス品質の低下やクレームの原因になってしまうリスクもあります。
ワンオペ店舗には、「ほどよい集客が見込める落ち着いた立地」が合っています。以下のような場所が現実的です:
- ビジネス街の裏通り(ランチや1人飲み需要が狙える)
- 住宅地エリアの路面店(常連客の獲得がしやすい)
- 地元密着型の商店街の一角
また、家賃も立地に大きく左右されるため、客単価とのバランスがとれるエリアを選ぶことがポイントです。たとえば、月の家賃が15万円で客単価が1,000円なら、月に150人の来客でトントン。その数字を「一人でさばけるか?」という目線で逆算しましょう。
3. 物件選びで見落としがちなポイントとその対策
ワンオペ飲食店を成功させるためには、立地や広さといった「目に見える要素」だけではなく、契約内容やインフラの状態など、見落とされがちなポイントにも注意が必要です。ここでは、実際に物件選びで失敗しやすいポイントとその対策を詳しく解説していきます。
既存設備の状態とインフラ確認
内見時に忘れてはいけないのが、既存設備の状態やインフラの確認です。たとえば、
- 電気容量は調理機器に対応できるか?
- 排水設備は油分を含んだ水を処理できる仕様か?
- ガスの種類(都市ガス or プロパン)は厨房機器と合っているか?
- 換気・排気設備は十分に機能しているか?
これらが不十分だと、開業後に思わぬ追加工事が必要になり、想定外のコスト増や工期遅延を招くことがあります。
とくに注意したいのは「換気」と「排水」。臭いや煙が外に漏れる設計だと、近隣トラブルに発展するリスクもあります。内見時は厨房の設備だけでなく、ダクトやグリーストラップの位置・状態にも目を向けることが大切です。
契約条件の確認(改装可否・解約条件など)
「よし、この物件にしよう」と思ったとき、見落とされがちなのが契約条件の詳細です。以下のようなポイントは、必ずチェックしておきましょう:
- 内装・外装の改装は自由にできるか?
- 看板の設置に制限はないか?
- 原状回復の範囲はどこまでか?
- 中途解約に違約金は発生するか?
たとえば、「改装不可」の物件では、ワンオペ向けのレイアウトに変更できない可能性もあります。また、「スケルトン渡し」か「居抜き」かによって、初期費用が大きく変動する点も重要です。
契約書は必ずすみずみまで読み込み、不明点は遠慮せず貸主または仲介業者に確認するようにしましょう。営業許可の取得に関わる項目も含まれるため、ここを怠ると営業開始自体ができなくなるケースもあります。
周辺環境と競合状況のリサーチ
物件そのものだけでなく、周辺の環境と競合の存在も、飲食店の成否を大きく左右します。
- 近くに同業態の店舗が密集していないか?
- 周辺はオフィス街、住宅街、学生街のどれか?
- 時間帯によって人の流れがどう変化するか?
- 駅やバス停、駐輪場との距離は?
また、夜間の雰囲気や治安も必ず確認しておきましょう。昼と夜でまったく表情が変わるエリアも少なくありません。
Googleマップや食べログ・Rettyなどを活用して、同じエリアにどんな店があるかを事前にチェックするのも効果的です。自店のコンセプトと被らないか?逆にニッチなポジションを取れるか?**「差別化が可能な立地かどうか」**を冷静に判断する必要があります。
4. ワンオペ物件の探し方・不動産会社との付き合い方
理想の物件が見つからなければ、どんなに優れたコンセプトやメニューを持っていても、ワンオペ飲食店は成立しません。ここでは、ワンオペに最適な物件を効率よく見つけるための具体的な方法と、不動産会社との上手な付き合い方をご紹介します。
内見時にチェックすべき7つのポイント
内見は、単に「雰囲気を見る」ためのものではありません。営業時をリアルに想定しながら、以下の7つの項目を細かくチェックするようにしましょう。
- 客席から厨房が見渡せるか?(視認性)
- 厨房内での動線がスムーズか?(調理・配膳の導線)
- 電気・ガス・水道の容量と配管の状態
- 排気・換気設備の性能と位置
- トイレの有無・清潔さ(設置義務にも関わる)
- 改装の自由度(壁やカウンターの取り外し可否)
- 建物自体の古さ・老朽化リスク
これらを確認せずに契約してしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔する原因になります。可能であれば、飲食店開業の経験がある第三者と一緒に内見を行うと、より客観的にチェックできるでしょう。
不動産会社に伝えるべき条件と交渉術
不動産会社に物件探しを依頼する際には、「ワンオペ向き」であることを明確に伝えることが重要です。ただ「10坪以下の飲食可物件」と伝えるだけでは、適切な候補は出てきません。
以下のような具体的な条件をリストアップして伝えましょう:
- 希望坪数(例:6〜8坪)
- カウンター中心のレイアウトが可能な物件
- 厨房・ホールの一体化がしやすい構造
- 排気・トイレ設備の有無
- 居抜き or スケルトンの希望
- 改装可能な物件かどうか
また、内見時や契約前の交渉では、「入居前に貸主側で対応してもらえる工事」や「家賃交渉の余地」があるかも確認しましょう。飲食業に慣れていない業者の場合は、具体的なイメージ図や参考写真を提示することで、意図が伝わりやすくなります。
「ワンオペに強い」仲介業者の探し方
一般的な不動産ポータルサイトでは、ワンオペに最適な物件を見つけるのはなかなか難しいのが現実です。そこで頼りになるのが、飲食店専門の仲介業者や内装会社が運営する物件紹介サービスです。
以下のようなサービスは、ワンオペ向きの居抜き物件や小型店舗情報に強みがあります:
これらを活用することで、希望に近いワンオペ対応物件に出会える可能性が格段に上がります。とくにテンポス系列は、厨房機器や内装相談も一貫して受けられるため、初めての開業にも心強い存在です。
5. 【まとめ】ワンオペ飲食店は「物件選び」で9割決まる
飲食店を一人で運営するワンオペスタイルは、人手不足やコスト高騰の時代において、非常に合理的かつ現実的な選択肢です。しかし、それを実現できるかどうかは、最初の「物件選び」にかかっていると言っても過言ではありません。
ここで、これまでのポイントをあらためて整理しておきましょう。
レイアウト・坪数・立地の再確認
ワンオペ向き物件を見極めるには、以下の3要素のバランスが非常に重要です。
- レイアウト: カウンター中心で一人でも完結できる導線設計が必須
- 坪数: 5〜10坪が理想。広すぎず狭すぎず、作業とサービスのバランスが取れる
- 立地: 集客数より「一人で回し切れる範囲」を重視。過度な繁華街は避けるのも一手
これらが噛み合って初めて、効率的かつ快適なワンオペ営業が実現します。
開業前にやるべき準備リスト
物件を見つけたら、開業に向けて以下のような準備を計画的に進めましょう。
- 事業計画書と収支シミュレーションの作成
- 店舗レイアウト案とオペレーション設計
- 保健所や消防への事前相談・申請準備
- 設備・内装業者との打ち合わせ
- 開業資金(融資・補助金)の確保
とくにワンオペでは、「自分が動けない時間のリスク」を見越して、最初から仕組みでカバーする設計が重要です。
「物件ありき」の店舗設計マインドが重要
最後に強調したいのは、理想のメニューやサービスがあっても、実現できる物件でなければ意味がないということです。
つまり、メニューやコンセプトを物件に“合わせにいく”柔軟性が、ワンオペ開業には求められます。店舗づくりの主導権は「夢」ではなく、「現実の物件条件」にあります。そこにフィットさせながら、無理なく続けられるモデルを設計していくこと。それこそが、ワンオペ飲食店成功の最大の鍵なのです。