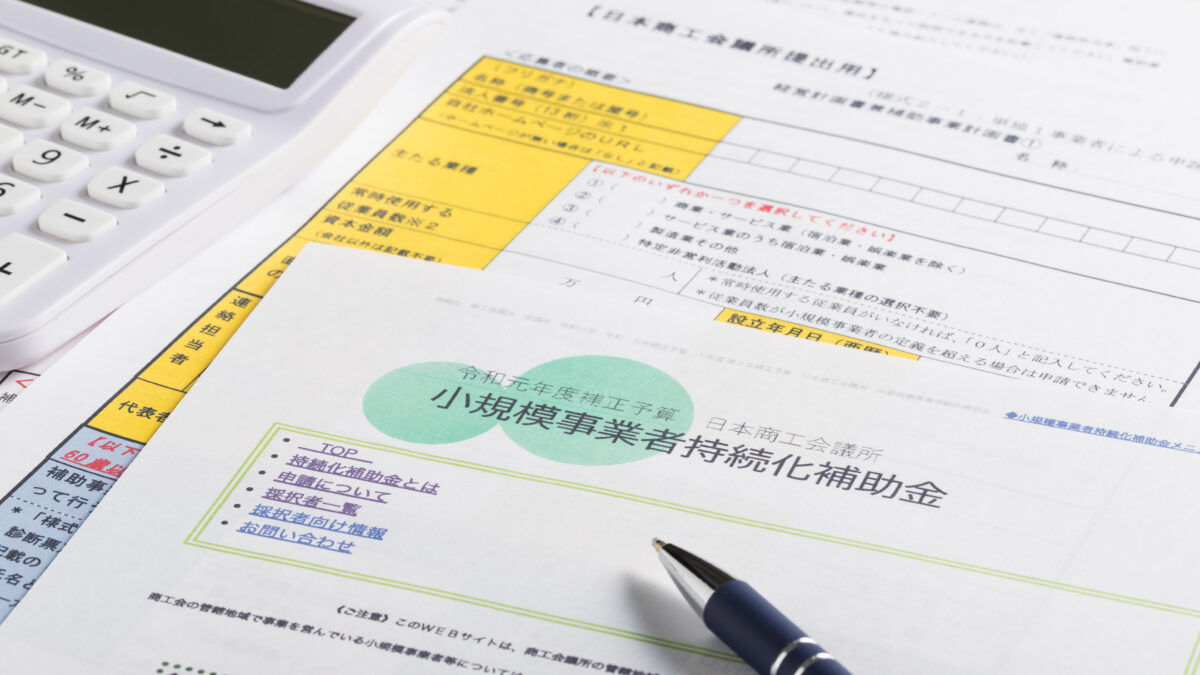理想の店をつくるとき、最初にぶつかる壁はたいてい「お金」です。
「このカウンターにしたい」「厨房機器はここまで揃えたい」「外観もきれいにしたい」——そう思っても、見積もりを見た瞬間に現実に引き戻されるオーナーさんは少なくありません。
そんなときに知っておきたいのが、国や自治体が用意している補助金・助成金制度です。
飲食店のように設備投資が重くなりがちな業種でも、目的に合った制度を選べば自己負担を抑えて店舗づくりを進めることができます。
しかも返済は不要。
うまく使えば、開業を早めたり、諦めていた改装を実現したりすることも可能です。
とはいえ、補助金は「種類が多い」「公募時期が変わる」「条件が複雑」と感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、細かな数字や年度に左右されない形で、飲食店が使いやすい主要な補助金・助成金をフェーズ別に整理しました。
開業なのか、改装なのか、機材導入なのか——目的が決まれば、選ぶ制度はぐっと絞りやすくなります。
このあと、飲食店が押さえておきたい基本の考え方から、代表的な制度の概要、申請の進め方まで順に解説します。
読み終えるころには、「今チェックしておくべき補助金」が自分で判断できるようになるはずです。
飲食店で使える補助金・助成金とは?
補助金や助成金は、店舗運営や投資の一部を公的に支援する制度です。
返済の必要がなく、飲食業の成長や地域の活性化を目的として設計されています。
まず押さえておきたいのは、「補助金」と「助成金」は似ているようで仕組みが異なるということ。
補助金は、審査を経て採択される競争型の支援です。
主に設備投資や新規事業、デジタル化など、事業の発展につながる取り組みが対象になります。
助成金は、条件を満たせば比較的受け取りやすい支援制度です。
人材育成や雇用の維持、働き方改革など、人的な取り組みを後押しする目的で設けられています。
飲食業では、開業・改装・機器更新・IT導入・スタッフ教育など、さまざまな場面でこれらの制度を利用することができます。
募集は国(中小企業庁・厚生労働省)だけでなく、都道府県や市区町村、商工会議所などでも行われています。
つまり、「自分の地域で」「自分の目的に合う」補助金を探すのが第一歩です。
そのためには、まずどのフェーズでどんな費用を使いたいのかを明確にしましょう。
開業か、リニューアルか、機材投資か——方向を決めるだけで、候補となる補助金は自然と絞り込めます。
次章では、まず開業時に活用できる代表的な制度を紹介していきます。
開業フェーズで使える補助金・助成金
飲食店を始めるとき、もっとも負担が大きいのが「初期費用」です。
物件取得費や内外装工事、厨房機器の購入など、数百万円単位の支出が発生します。
そんな開業準備を支える制度として、代表的なものが次の2つです。
小規模事業者持続化補助金
飲食店の開業や新サービスの立ち上げで広く利用されている補助金です。
販促費、チラシ、ホームページ、内外装工事など、小規模店舗のスタートアップに必要な経費を幅広くカバーします。
対象は、これから創業する人や個人経営の飲食店など。
商工会議所や商工会のサポートを受けながら申請するケースが多く、初めての人でも比較的挑戦しやすい制度です。
ポイントは、「どんな地域に」「どんな価値を生む店をつくるか」を明確にすること。
地域に根ざした店舗づくりを掲げると、採択の可能性が高まります。
創業支援補助金(自治体制度)
もうひとつ注目したいのが、各自治体が実施する創業支援制度です。
市区町村によって名称や条件は異なりますが、開業初期の資金負担を軽くするための支援として用意されています。
応募時に、商工会議所への登録や事業計画書の提出が求められることもあります。
また、面談やセミナー受講を条件にしている地域もあり、制度を活用しながら経営知識を学べるのも特徴です。
「〇〇市 創業補助金」「〇〇区 開業支援」などで検索すると、最新情報を確認できます。
💡ポイント:
開業支援系の補助金は、申請できる期間が限られている場合が多いです。
開業を決めた段階で早めに情報をチェックしておくことが、チャンスを逃さないコツです。
次章では、既存店舗の「改装・リニューアル」に使える補助金を紹介します。
改装・リニューアルに使える補助金
店舗を長く続けていくと、「内装を一新したい」「動線を改善したい」「新しい業態に変えたい」と感じるタイミングが訪れます。
そんなときに役立つのが、改装やリニューアルを支援する補助金制度です。
単なる修繕費ではなく、事業の成長や地域の活性化につながる“前向きな改装”であれば、対象になる可能性があります。
事業再構築補助金
飲食店のリニューアルや新しいコンセプトへの挑戦を支援する代表的な制度です。
「既存店舗を改装して別の業態を始めたい」「テイクアウト対応に設備を変えたい」など、事業の方向性を変える投資が対象となるケースがあります。
コロナ禍以降、多くの飲食店がこの制度を活用して新たな展開に踏み出しました。
特徴は、単なるリフォームではなく、新たな価値を生む取り組みであるかが重視される点。
厨房や内装の改修費用も含められる場合があり、「お店の未来を描く改装」を後押ししてくれる制度といえます。
地域商店街活性化支援事業
地域の商店街が持つ魅力やにぎわいを取り戻すために設けられた制度です。
老朽化した店舗の改装や、空き店舗を活用した新しい出店、商店街全体のデザイン統一など、まちの活性化につながる取り組みを支援します。
対象となる事業は幅広く、外観・看板・照明などの改修、通路の整備、バリアフリー対応なども含まれます。
さらに、イベント開催や共同販促など、地域一体での取り組みが評価されやすい点も特徴です。
個店単体でも申請できますが、商店街振興組合や自治体と連携して実施するプロジェクトのほうが採択されやすい傾向にあります。
「自店の改装を通して地域を元気にする」——そんな視点を持つ店舗にとって、心強い支援制度といえるでしょう。
💡ポイント:
改装関連の補助金は、「新規性」「地域貢献」「デザイン性」などが審査で評価されやすい傾向があります。
見た目の刷新だけでなく、動線改善やユニバーサルデザインの導入といった機能的価値の向上も意識して計画を立てましょう。
次の章では、厨房機器やデジタルツール導入など、設備投資フェーズで使える補助金を紹介します。
設備・機材導入に使える補助金
飲食店の運営では、日々のオペレーション効率を左右する「設備投資」も欠かせません。
厨房機器の老朽化や、省エネ対応、デジタル化など、店舗の質を高めるための投資を支援する制度がいくつかあります。
ここでは、特に活用されやすい3つの補助金を紹介します。
ものづくり補助金
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」。
製造業だけでなく、飲食店や小売業など、幅広い業種の生産性向上を目的とした設備投資を支援する制度です。
飲食店では、厨房機器・焙煎機・スチコン・自動調理システムなど、
業務効率や品質向上につながる設備導入で使われるケースが多くあります。
たとえば、
- 調理の自動化による人手不足対策
- 焙煎や抽出の安定化による品質維持
- 仕込み時間短縮による回転率アップ
といった目的での活用が一般的です。
また、ITツールの導入など、業務の効率化を目的とした投資も対象になる場合があります。
申請の際は、単に「新しい機械を買いたい」ではなく、
「投資によってどんな効果を得るのか」を明確にすることが大切です。
生産性の向上や顧客体験の改善など、成果を具体的に示すことで採択率が上がります。
商工会議所や中小企業診断士など、専門家のサポートを受けながら計画を立てるとより安心です。
IT導入補助金
飲食店のデジタル化・DX化を後押しする代表的な制度です。
予約システム、POSレジ、モバイルオーダー、在庫・勤怠管理ツールなど、
ITツールを活用して業務を効率化する取り組みが対象になります。
申請は、国に登録された「IT導入支援事業者」と呼ばれる専門事業者を通じて行うのが一般的です。
自店に合ったツールを選び、どんな課題を解決できるのかを明確にしておくと、採択の可能性が高まります。
最近では、キャッシュレス決済やモバイルオーダー対応など、顧客体験の向上を目的にした導入も増えています。
省エネ・環境対応型補助金
「省エネ・環境対応型補助金」は、エネルギー使用量やCO₂排出削減を目的とした制度です。
経済産業省(資源エネルギー庁)が実施し、高効率な設備への更新や省エネ改修が支援対象となります。
飲食店では、空調・冷蔵設備・給湯器・照明の更新などに活用されることが多く、
老朽化した機器を省エネ型に替えることで、電力消費を抑えながら快適な環境を維持できます。
「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」による電力使用の可視化・最適化も支援対象に含まれる場合があります。
複数店舗をまとめて申請できるケースもあり、チェーン店にも有効です。
申請では、どの設備をどう改善すればエネルギーが減るのかを数値で説明することが大切です。
環境に配慮しつつコストを抑えたい店舗におすすめの補助金です。
💡ポイント:
いずれの制度も、「効率化」「省力化」「環境改善」といったキーワードが重視されます。
単なる機器更新ではなく、店舗経営の質を高める投資として位置づけることが成功の鍵です。
次の章では、実際に補助金を申請する際の流れと、採択率を上げるためのポイントを紹介します。
補助金活用の流れと申請のコツ
補助金を上手に活用するには、流れを理解し、早めに準備を進めることが大切です。
申請のタイミングを逃すと次の公募まで数か月待つこともあるため、スケジュール感を意識しましょう。
申請の基本ステップ
- 自分に合う補助金を選ぶ 目的(開業・改装・設備導入など)を明確にして、条件に合う制度を確認します。
- 公募要領・募集時期を調べる 年度や募集回によって内容が変わることがあるため、公式サイトを必ずチェックしましょう。
- 事業計画書を作成する 投資の目的や期待する効果を、できるだけ具体的にまとめます。
- 書類を提出する(多くは電子申請) 必要書類をそろえ、期限内に申請。提出前に不備がないか再確認します。
- 採択・事業実施・報告 採択後に実際の事業を行い、終了後に実績報告を提出します。
💡補助金は後払い(精算払い)が基本です。
いったん自己資金で立て替える必要がある点に注意しましょう。
採択されやすい計画書のポイント
- 自社の課題を明確に示す
- 投資による成果(売上・回転率・人件費削減など)を数値で書く
- 地域貢献や雇用創出など、社会的意義を加える
特に飲食店の場合、「地域との関わり」「持続可能な店舗運営」などを盛り込むと評価されやすくなります。
相談できる窓口
申請前に、商工会議所・商工会・自治体の産業振興課などへ相談するのがおすすめです。
無料でアドバイスを受けられるうえ、申請書の方向性も確認できます。
また、補助金に詳しい中小企業診断士や税理士に相談するのも効果的です。
専門家のサポートを受けながら準備を進めれば、初めての申請でも安心です。
次の章では、この記事全体のまとめとして、補助金を店舗づくりの戦略にどう生かすかを解説します。
まとめ|補助金を味方に、理想の店舗を形にしよう
補助金は、飲食店にとって“攻めの資金戦略”です。
うまく活用すれば、開業資金を抑えたり、改装や機材導入を計画的に進めたりできます。
ただし、申請時期や対象条件を理解しないまま動くと、せっかくのチャンスを逃すこともあります。
まずは「どのフェーズで、何に投資したいのか」を整理し、自分に合う制度を選ぶことが大切です。
最新の募集情報は、中小企業庁や各自治体の公式サイトで必ず確認しましょう。
わからない場合は、商工会議所や専門家に相談するのもおすすめです。
補助金を上手に使うことは、単なる資金調達ではなく、店舗づくりの戦略を立てることでもあります。
「守る経営」から「育てる経営」へ。
あなたの理想の店舗を、補助金という追い風で形にしていきましょう。