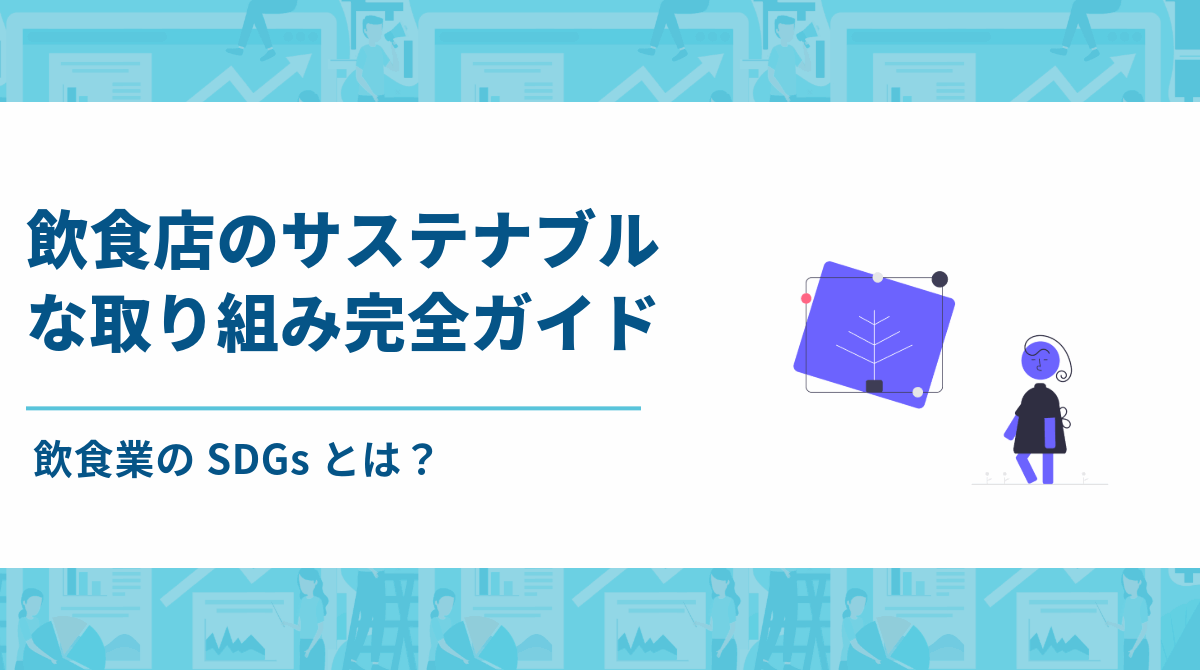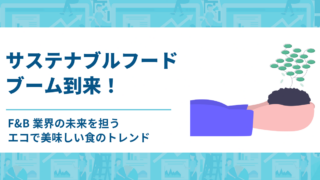近年、さまざまな業界で注目を集めている「SDGs(エスディージーズ)」。持続可能な社会の実現を目指すこの取り組みは、飲食業界とも無縁ではありません。
環境や社会に配慮した経営は、もはや一部の先進的な店舗だけの話ではなく、これからの「選ばれる飲食店」の新しい基準になりつつあります。
「SDGsって大事なのはわかるけど、実際に何から始めればいいのか分からない」
「うちのような小さな店でも取り組む意味はあるのだろうか?」
そんな疑問を持つ方のために、本記事では飲食店が今すぐ始められるSDGsの取り組みについて、わかりやすく解説していきます。
SDGsとは?飲食業とどんな関係があるのか
SDGsの基本的な考え方
SDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)は、2015年に国連で採択された、2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットからなる国際目標です。
貧困や飢餓、環境問題、ジェンダー平等、働きがいのある労働環境の提供など、幅広い社会課題に対する解決策が示されています。
そのなかには、「つくる責任 つかう責任」「飢餓をゼロに」「気候変動に具体的な対策を」など、飲食業と深い関係のあるテーマが多く含まれています。
なぜ今、飲食業がSDGsに注目されるのか
飲食業は、食材の調達から調理、提供、廃棄まで、多くのリソースを使用し、環境や地域社会に大きな影響を与える業種です。
そのため、SDGsへの貢献度が高く、取り組み次第で大きな変化を生み出せる分野といえるでしょう。
また、消費者の価値観も大きく変化しています。環境や社会に配慮した店を選ぶ傾向は年々高まっており、サステナビリティを意識した経営は、集客力やブランド力にも直結します。
たとえば、以下の記事で紹介しているサステナブルフードのトレンドも、消費者の意識変化を象徴するものです:
つまり、SDGsは「大企業だけの話」ではなく、個人経営の小さな飲食店にとっても、今や無視できない経営テーマとなっているのです。
SDGsに取り組むメリットとは?
SDGsの取り組みは、社会貢献という大義だけでなく、実際の店舗経営にもプラスの効果をもたらします。ここでは、飲食店がSDGsに取り組むことで得られる主なメリットを3つ紹介します。
信頼性とブランド価値の向上
現代の消費者は、単に「美味しい・安い」だけではなく、その店がどのような価値観を持ち、社会や環境にどう向き合っているかも重視する傾向があります。
たとえば、「地産地消にこだわっています」「フードロス削減に取り組んでいます」といった姿勢は、共感や信頼につながり、リピーターの獲得にも効果的です。
さらに、SDGsに積極的な店舗は、地元メディアやSNSでも話題になりやすく、広報面でも優位性を持つことができます。
顧客ニーズへの対応と集客力アップ
サステナビリティを意識する消費者層は年々増加しており、とくに20〜40代の都市部在住者やファミリー層の間では、「環境配慮型のサービスを選びたい」という意識が高まっています。
SDGsを実践することで、こうした層の関心を惹きつけ、新たな顧客層を開拓するチャンスが生まれます。
たとえば以下のようなシチュエーションで差別化が可能です:
- SNSで「エコなカフェ」として拡散される
- 子育て世代が「安心して通えるお店」として選ぶ
- 環境意識の高い企業からのケータリング依頼が増える
スタッフの定着率や働きがいにもプラス
SDGsの目標には「働きがいも経済成長も(目標8)」や「ジェンダー平等(目標5)」といった、労働環境に関する内容も多く含まれています。
スタッフにとっても、社会に貢献できる職場であることは、モチベーション向上や定着率の向上につながります。
「うちの仕事は社会の役に立っている」と感じられる環境は、人材不足に悩む飲食業界にとって大きな強みです。
また、SDGsに関する取り組みをスタッフと共有することで、チーム意識や職場の一体感も高まりやすくなります。
飲食店で始めやすいサステナブルな取り組み
「SDGs」と聞くと大がかりなことを想像しがちですが、実際は小さなことからでも立派な貢献になります。ここでは、飲食店が今日から始められる現実的な取り組みを紹介します。
食材ロスを減らす工夫
飲食業における食品ロスは大きな社会課題のひとつです。ロスを減らすことは、SDGs「12. つくる責任 つかう責任」に直結します。
主な取り組み例:
- 仕込み量やメニュー構成を見直し、注文率の高い商品を中心に展開
- 一部食材を使い切るための「日替わりまかない」や「残り福メニュー」
- お客様への持ち帰り容器(ドギーバッグ)提供
これらはコスト削減にもつながり、一石二鳥の施策です。
地元食材やオーガニック素材の活用
「地産地消」はSDGsの観点でも非常に有効です。地元食材の活用は、輸送に伴うCO2排出を削減できるだけでなく、地域経済の活性化にも貢献します。
オーガニックや減農薬の素材を取り入れることで、健康志向の顧客層にもアピールできます。
店内の黒板やSNSで「○○産の野菜を使用しています」と発信すれば、ストーリーのある商品づくりとしても効果的です。
環境に配慮した容器・備品の使用
テイクアウトやデリバリー需要が高まる中で、プラスチック容器や使い捨て備品の見直しは欠かせません。
おすすめの代替素材:
- バガス(サトウキビ繊維)や紙製の弁当容器
- 木製やリユース可能なカトラリー
- 再生紙ナプキン、リサイクルペーパーのレシート
初期コストが多少かかっても、「エコなお店」としての認知が高まり、顧客の共感につながります。
省エネ・節水の工夫
光熱費は飲食店にとって大きな固定費。省エネ・節水の取り組みは、環境だけでなく経営面でも即効性があります。
簡単に始められる例:
- LED照明や省エネエアコンの導入
- 閉店後の電源オフ・タイマー設定の徹底
- 食器洗浄のタイミングをまとめることでの節水
小さな積み重ねが、持続可能な経営につながる第一歩となります。
スタッフ教育やチームでの目標設定
サステナブルな店舗運営には、スタッフ全員の意識が不可欠です。一人で抱え込まず、チームとして取り組む体制を整えることが成功のカギとなります。
- 定期的なミーティングでSDGsの話題を共有
- 社内で「フードロスチャレンジ」「節電目標」などを設定
- 目に見える形で成果を掲示し、モチベーション維持
スタッフ自身が**「自分たちも社会に貢献している」と実感できること**が、やりがいのある職場づくりにもつながります。
飲食店で始めやすいサステナブルな取り組み
「SDGs」と聞くと大がかりなことを想像しがちですが、実際は小さなことからでも立派な貢献になります。ここでは、飲食店が今日から始められる現実的な取り組みを紹介します。
食材ロスを減らす工夫
飲食業における食品ロスは大きな社会課題のひとつです。ロスを減らすことは、SDGs「12. つくる責任 つかう責任」に直結します。
主な取り組み例:
- 仕込み量やメニュー構成を見直し、注文率の高い商品を中心に展開
- 一部食材を使い切るための**「日替わりまかない」や「残り福メニュー」**
- お客様への持ち帰り容器(ドギーバッグ)提供
これらはコスト削減にもつながり、一石二鳥の施策です。
地元食材やオーガニック素材の活用
「地産地消」はSDGsの観点でも非常に有効です。地元食材の活用は、輸送に伴うCO2排出を削減できるだけでなく、地域経済の活性化にも貢献します。
オーガニックや減農薬の素材を取り入れることで、健康志向の顧客層にもアピールできます。
店内の黒板やSNSで「○○産の野菜を使用しています」と発信すれば、ストーリーのある商品づくりとしても効果的です。
環境に配慮した容器・備品の使用
テイクアウトやデリバリー需要が高まる中で、プラスチック容器や使い捨て備品の見直しは欠かせません。
おすすめの代替素材:
- バガス(サトウキビ繊維)や紙製の弁当容器
- 木製やリユース可能なカトラリー
- 再生紙ナプキン、リサイクルペーパーのレシート
初期コストが多少かかっても、「エコなお店」としての認知が高まり、顧客の共感につながります。
省エネ・節水の工夫
光熱費は飲食店にとって大きな固定費。省エネ・節水の取り組みは、環境だけでなく経営面でも即効性があります。
簡単に始められる例:
- LED照明や省エネエアコンの導入
- 閉店後の電源オフ・タイマー設定の徹底
- 食器洗浄のタイミングをまとめることでの節水
小さな積み重ねが、持続可能な経営につながる第一歩となります。
スタッフ教育やチームでの目標設定
サステナブルな店舗運営には、スタッフ全員の意識が不可欠です。一人で抱え込まず、チームとして取り組む体制を整えることが成功のカギとなります。
- 定期的なミーティングでSDGsの話題を共有
- 社内で「フードロスチャレンジ」「節電目標」などを設定
- 目に見える形で成果を掲示し、モチベーション維持
スタッフ自身が**「自分たちも社会に貢献している」と実感できること**が、やりがいのある職場づくりにもつながります。
まとめ|未来の飲食業のために、今日からできる一歩を
SDGsは、世界の大企業だけでなく、地域の小さな飲食店にとっても関係のある、重要なテーマです。地球環境や社会、そして自分たちの働く場やお客様との関係を大切にしながら、持続可能な飲食店づくりを目指すことは、これからの時代において“当たり前”になっていくでしょう。
本記事で紹介したように、サステナブルな取り組みは大げさなことではなく、食材の使い方・設備の見直し・働き方の工夫など、身近なことから始められる内容ばかりです。
そして何より、「社会にいいことをしているお店」は、お客様やスタッフからも選ばれる存在になります。信頼され、応援され、長く愛される飲食店として成長していくためにも、まずは今日からできる小さなアクションを、ぜひ始めてみてください。