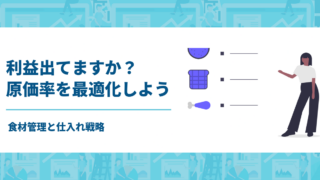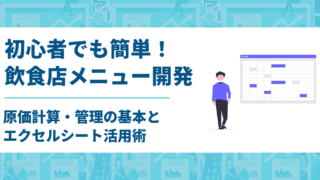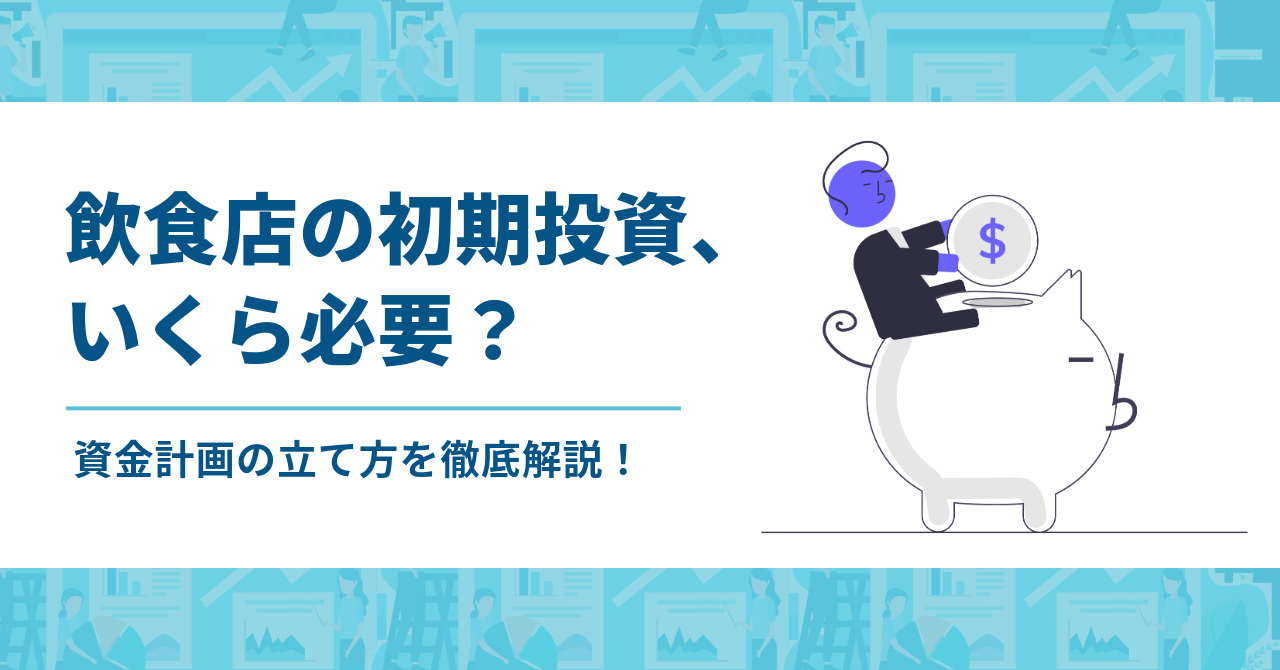カフェ経営で「黒字になる」とは?|まずは基本の考え方を理解しよう
「カフェって儲かるの?」——カフェ開業を目指す人の多くが抱く素朴な疑問です。
答えはシンプルで、「売上が支出を上回れば黒字、下回れば赤字」です。ですが、実際に黒字を出すには、ただコーヒーを売ればいいというわけではありません。
ここではまず、「黒字経営とは何か」「そのために必要な数字の見方」について、初心者にもわかりやすく解説します。
黒字=「損益分岐点を超えること」
黒字か赤字かを分ける最大のポイントは、「損益分岐点」を超えられるかどうかにあります。
損益分岐点とは、売上と経費がちょうど同じになる地点のこと。これを超えると利益(黒字)が出て、下回ると赤字になります。
たとえば、月に50万円の経費(家賃・人件費・仕入れなど)がかかる場合、月商50万円を超えないと黒字にはなりません。
損益分岐点の計算式は、以下の通りです。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)ここでいう「固定費」とは、売上の有無にかかわらず発生する費用(家賃、人件費の固定部分など)。「変動費率」は売上に応じて増減する費用(原材料費など)を売上で割ったものです。
たとえば、固定費が30万円、変動費率が40%なら…
損益分岐点=30万円 ÷(1 − 0.4)= 50万円この場合、月商50万円を超えると黒字、下回ると赤字になります。
売上・原価・固定費・変動費の関係
利益を出すためには、売上だけでなく、費用の内訳を正しく把握することが大切です。特にカフェ経営では、以下の4つの指標が重要になります。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 売上 | コーヒーやフード、物販などの総売上 |
| 原価 | 食材・飲料などの仕入れコスト(変動費) |
| 固定費 | 家賃、人件費(最低限の人員)、水道光熱費など、売上に関係なくかかる費用 |
| 変動費 | 原価に加え、売上に応じて変わる包装代、販促費など |
カフェ経営は「薄利多売」になりやすいため、少しのコスト増や客数減でもすぐに赤字に転落するリスクがあります。だからこそ、各項目を意識して設計し、バランスをとることが黒字化のカギになります。
飲食業(特にカフェ)の利益構造の特徴とは?
飲食業の中でもカフェは「原価率が比較的低く、利益を出しやすい業態」と言われます。
コーヒーやドリンク類の原価は20〜30%程度で済むことが多く、食材ロスも少ないため、上手に運営すれば利益率は高くできる業態です。
一方で、客単価は一般的に1,000円未満となるケースが多く、「回転率」と「リピート率」によって収益性が大きく左右されます。
また、家賃や人件費の比重が高くなる都市部では、少しのずれで赤字に転じることもあります。
こうした点からも、「損益分岐点を正しく知り、数字で経営判断をする視点」がとても重要なのです。
ここまでで、「黒字になるとはどういうことか?」の基本が理解できたかと思います。
次のセクションでは、実際に月いくら売上があれば黒字になるのか?をモデルケースで解説していきます。
カフェは月いくら売上があれば黒字?|モデルケースで試算してみよう
「結局、毎月いくら売り上げればカフェは黒字になるのか?」
これは開業前の人だけでなく、すでにお店を運営している人にとっても非常に重要な問いです。
この章では、一般的な小規模カフェを想定した数字を使って、黒字ラインをシミュレーションしてみましょう。
一般的な小規模カフェのコスト構造
まず、仮に都内で10坪程度のカフェを一人または夫婦などで運営しているケースを想定します。ここでは、月あたりのコストをざっくり以下のように設定します。
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 家賃 | 15万円 |
| 水道光熱費 | 2万円 |
| 材料費(原価) | 売上の30%程度 |
| 人件費 | 10万円(自分の取り分を含まない最低限) |
| 雑費(消耗品・宣伝など) | 3万円 |
| 合計固定費 | 約30万円 |
この場合、固定費が約30万円です。
そして、売上の30%が原価(変動費)だと仮定します。
では、実際の売上目標はどのくらいになるのでしょうか?
月商60万円での黒字ライン試算
損益分岐点の式に当てはめてみましょう。
損益分岐点 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)
= 30万円 ÷(1 − 0.3)
= 約42.9万円つまり、月商約43万円が最低限の黒字ラインとなります。
ただし、これは“利益ゼロ”のライン。ここからさらに自身の給与を確保するとなると、最低でも月商60万円程度は必要になってくると考えられます。
例えば、月商60万円で原価30%なら材料費は18万円。残りの42万円から固定費30万円を引くと、12万円が「営業利益」となります。
この12万円から自分の取り分(給与)を出すとすると、それなりにやりくりしないと十分な生活資金は残りません。このことからも、月商60万円は“最低ライン”と考えておくのが無難です。
月商100万円ならどうなる?利益率を比較
では、月商100万円を達成した場合はどうでしょうか。
材料費(原価30%)が30万円。
固定費が30万円と仮定すれば、残りは40万円の営業利益になります。
ここから税金や必要経費を差し引いたとしても、十分に生活費や次の投資に回せる利益が残ることがわかります。
つまり、月商100万円を超えられれば、「経営者としての報酬」「事業の安定」「設備投資や拡張の原資」が確保できる水準と言えるでしょう。
もちろん、立地や業態、物件規模によってこの数字は前後しますが、ひとつの目安として以下のように整理できます。
| 月商 | 状態 |
|---|---|
| 〜40万円 | 赤字の可能性大 |
| 〜60万円 | 損益分岐点を少し超える程度(最低ライン) |
| 〜80万円 | 経営者の報酬も確保できるが余裕は少ない |
| 100万円以上 | 安定経営・投資も可能な水準 |
このように、「月商いくらを目指すか」=「どのレベルの生活・経営を目指すか」とも言えます。
現実的な目標を立てるためにも、まずは自分の理想とするライフスタイルと店舗規模を明確にしておくことが重要です。
黒字経営を実現する5つのポイント|利益率を上げるには?
ここまでで、「月商〇万円で黒字化できる」という数値的な目安は見えてきたかと思います。
しかし、目標売上を立てただけでは利益は出ません。むしろ、利益が出るかどうかは、日々の経営判断と設計次第です。
この章では、実際にカフェ経営で黒字を出していくための「利益率を高める具体的なポイント」を5つに分けてご紹介します。
- 原価率を下げる(食材選定・ドリンク中心設計)
原価を抑えることは、利益率の改善に直結します。特に、カフェにおいては「ドリンク中心」のメニュー構成が強みになります。
たとえば、ハンドドリップコーヒーは原価が20〜30%程度に抑えられる上、作り置き不要でロスも出にくい商品です。
一方で、フードメニューは仕込みや保存の管理が必要になり、ロスも出やすくなります。
「軽食+ドリンクのセット販売」などで原価率のバランスを取る工夫が求められます。
また、業務用食材の活用、仕入先の見直し、ロス削減のための在庫管理の徹底など、小さな改善の積み重ねが原価率を大きく左右します。
- 固定費を抑える(物件選び・スタッフ配置)
固定費、特に家賃と人件費は、長期的に黒字を圧迫しがちです。
物件選びの段階から「安すぎず、高すぎず」を見極めることが重要。駅前の高額物件は集客には強い反面、売上が落ちた瞬間に一気に赤字になります。
また、家賃は「売上の10〜15%以内」が理想とされており、これを超えると収支バランスが崩れやすくなります。
人件費に関しては、オペレーションを簡素化し、「ワンオペでも回せる導線設計」にしておくと無駄な人件費を抑えることができます。
自分や家族で回せるような規模感にするのも、有効な手段のひとつです。
- 客単価を上げる(セット・限定商品・物販)
客単価を高める工夫も、黒字化に向けた有力な戦略です。
たとえば、以下のような工夫が効果的です。
- モーニングセットやアフタヌーンセットの導入
- 季節限定のドリンク・スイーツの展開
- コーヒー豆や自家製シロップなどの物販
「ついで買い」を誘発する設計ができると、1人あたりの売上が自然と増えていきます。
また、心理的なお得感(たとえば“ドリンク+ケーキで100円引き”など)を演出することで、無理のない価格アップが可能になります。
- 回転率を意識した導線設計
カフェはどうしても「長居されやすい」業態です。居心地の良さが売りでもありますが、席が回らないと売上が伸びません。
そのため、回転率を設計に組み込む工夫が必要になります。たとえば:
- カウンター席を設ける(単独客の回転を高める)
- 滞在時間が自然と短くなるイスやテーブルレイアウト
- 食後に出す無料サービスを絞る(長居のきっかけを減らす)
これらは「冷たい接客」とは違い、あくまで自然に回転を促す工夫です。回転率を意識すれば、限られた席数でも売上の最大化が狙えます。
- スモールスタート&段階的な拡大
最初から理想の店舗を目指して投資を膨らませすぎると、回収が困難になります。
開業初期は「必要最低限」でスタートし、黒字が安定してから徐々に規模やサービスを拡大するのが理想的です。
また、少人数・小面積の方が管理もシンプルになり、数字を把握しやすくなります。
クラウドファンディングや間借り営業から始めた成功事例も多く、「まずは黒字化の感覚を掴む」フェーズを大切にすることが、長期的な成功につながります。
カフェが赤字になる典型パターン|よくある失敗を避けよう
「一生の夢だったカフェ開業。でも、半年で赤字続きに…」
そんな話は決して珍しくありません。多くのカフェが開業から1年以内に撤退を余儀なくされる理由は、ほとんどが“想定外の赤字”による資金ショートです。
このセクションでは、カフェが赤字に陥る代表的なパターンを紹介します。事前にこれらを把握しておくことで、リスクを回避しやすくなります。
過剰投資(内装・什器)
「おしゃれな空間で勝負したい」「内装には妥協したくない」——この気持ちはとてもよくわかります。
しかし、開業初期に過剰な内装費や設備投資をしてしまうと、それだけで回収に時間がかかり、キャッシュフローが圧迫されます。
特にありがちなのが、以下のようなケースです。
- 300万円以上の内装工事費を一括で支払ってしまう
- 本格的なエスプレッソマシンや焙煎機を開業時から導入
- 使い切れない什器や装飾品をまとめ買い
「デザインは後からアップデートできる」「設備は黒字が出てからでも遅くない」という意識が、初期の健全経営を支える重要なマインドです。
売上見込みの甘さ
想定客数が毎日50人だったのに、実際には20人しか来なかった。
開業後にこうしたギャップに直面し、想定していた売上が立たないことは少なくありません。
売上の予測を立てる際は、常に「保守的に見積もる」ことが重要です。
理想ではなく、「平日が弱い」「雨の日はほぼゼロ」といった現実的なシナリオでシミュレーションしておくと、予想外の赤字を避けやすくなります。
家賃比率の高さ
家賃が売上の25〜30%を占めてしまうような場合、利益を出すのが非常に難しくなります。
一般的には「家賃は売上の10〜15%以内」が理想とされており、20%を超えると赤信号です。
立地が良い=成功しやすいとは限りません。
「少し駅から遠くても、固定費を抑えて利益を残す」戦略の方が、長く続けられる経営につながるケースもあります。
利益を出せるメニュー設計になっていない
いくらおしゃれで美味しくても、原価率が高く利益が残らないメニューばかりでは経営は成り立ちません。
たとえば、手の込んだプレートランチや生ケーキなどは、材料費がかかる上に人件費や仕込み時間も増えがちです。
一方、ドリンク中心・冷凍対応・作り置き可能なスイーツなどは、人件費・ロス・仕入れの面でも優秀です。
「お客様に提供したいもの」と「経営が回るもの」がズレすぎていないか。
メニュー構成を見直すことで、利益率が大きく改善されることもあります。
黒字経営を続けるために必要な視点|「数字」と「現場感」の両立
カフェ経営で一度黒字化できたとしても、それを継続することこそが本当の難しさです。
短期的に利益が出ても、慢心や油断があればすぐに赤字へと転落してしまいます。
この章では、黒字経営を「継続」するために、経営者が持つべき視点と習慣を紹介します。
毎月のPL(損益計算書)を見て判断できるようにする
まず何よりも大事なのは、数字に強くなることです。
カフェという現場は日々忙しく、コーヒーを淹れているだけで1日が終わってしまいがち。ですが、経営者である以上、「今月利益が出たのか」「何にどれだけ使っているのか」を毎月把握しなければなりません。
PL(損益計算書)といっても、難しい表を作る必要はありません。
以下のようなシンプルな形でも構いません。
| 項目 | 今月の金額 |
|---|---|
| 売上 | ¥820,000 |
| 材料費 | ¥240,000 |
| 家賃 | ¥150,000 |
| 光熱費 | ¥20,000 |
| 人件費 | ¥100,000 |
| 雑費 | ¥30,000 |
| 営業利益 | ¥280,000 |
こうした数字を毎月まとめておくことで、「どこが重くなっているのか」「無駄はどこか」が自然と見えるようになります。
売上だけでなく「利益率」を見るクセをつける
売上が上がったからといって、安心するのは危険です。
大切なのは「いくら売れたか」ではなく、「いくら残ったか」。
たとえば、A月は売上60万円・利益10万円、B月は売上50万円・利益15万円ということも普通にありえます。
つまり、利益率=効率の良さとも言えます。
売上を増やすよりも、まずは「利益率を上げる」ことを優先すると、無理のない経営が可能になります。
データ分析×現場改善でPDCAを回す
数字は分析して終わりではありません。
数字を見て、考え、改善を試みることで、はじめて意味を持ちます。
たとえば、
- 平日は売上が低い → モーニングセットやテイクアウトの強化
- 客単価が下がっている → セット販売や限定メニューの導入
- 回転率が悪い → 席配置や導線の見直し
など、数字と現場をつなぐ視点を持つことで、実効性のある改善策が見えてきます。
カフェ経営は感覚やセンスも大切ですが、それに加えて「数字から課題を見つける力」があれば、より強い店舗運営が可能になります。
より深く学びたい人へ|信頼できる情報源・ツール紹介
「もっと具体的に経営の数字を学びたい」「自分でも収支をシミュレーションしてみたい」——そんな方のために、信頼性の高い情報源と便利な無料ツールをご紹介します。
ここで紹介するものは、実際の飲食店経営でも活用できる実用性の高いものばかりです。
参考データ:中小企業庁「小規模事業者白書」
経営環境や売上・利益の実態、事業者の課題などを客観的に知りたい方は、中小企業庁が毎年発表している「小規模事業者白書」が非常に役立ちます。
- 中小飲食業の平均売上・利益率
- 黒字企業と赤字企業の差
- 収益改善のヒントとなる事例
など、統計と実例に基づいた内容が豊富です。
無料で使える売上シミュレーター・PLテンプレート
ExcelやGoogleスプレッドシートで利用できる売上・経費の計算テンプレートは、多くの自治体や商工会議所が配布しています。
以下は一例です:
これらのツールを使えば、自分の事業に合わせたリアルな損益シミュレーションが可能になります。
まとめ|月商〇万円で黒字化!無理なく利益を出すカフェ経営とは
カフェを黒字で経営するには、「なんとなく」ではなく、数字に基づいた明確な計画と実行力が求められます。
この記事では、カフェ経営の黒字ラインを理解するための損益分岐点の考え方から、実際に必要な月商の目安、そして利益を残すための戦略や失敗パターンまでを解説しました。
改めてポイントを整理してみましょう。
黒字ラインの目安と実現方法の再確認
- 最低ラインの月商は約60万円前後(家賃・人件費・原価率などによる)
- 月商100万円を超えると、報酬・投資・将来の備えまで視野に入る安定経営が可能
- 売上よりも利益率とコストのバランスが重要
- 固定費の見直し、メニュー戦略、オペレーション効率化が黒字のカギ
数字に基づいた経営で「継続できるカフェ」を目指そう
開業してから黒字を出すまでには、予想以上の時間や試行錯誤が必要なこともあります。
ですが、毎月数字を確認し、改善し続ける姿勢があれば、経営は少しずつ安定し、店舗にも自信が生まれてきます。
夢だけでなく、現実的な数字と向き合うこと。
これが「好きなことで生きていく」ための現実的な第一歩です。
無理なく、だけど着実に。あなたのカフェ経営が、長く続く幸せな仕事になりますように。