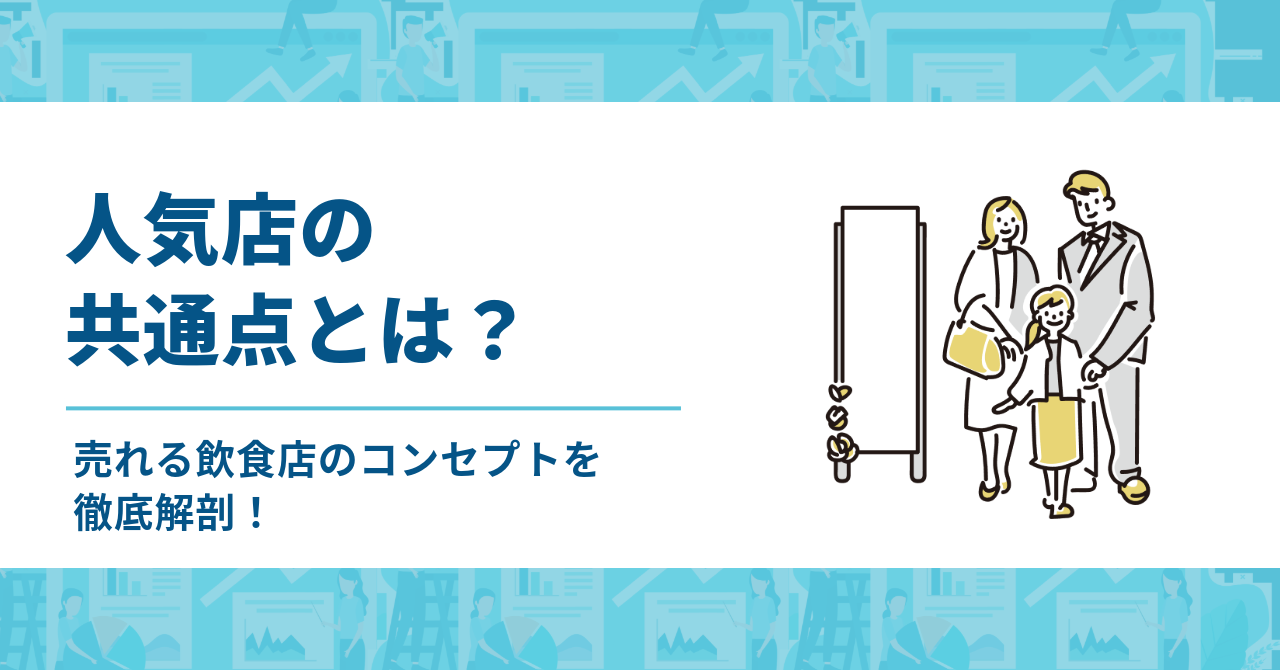内装で“売れるかどうか”が決まる時代へ
おしゃれな内装は、いまや「雰囲気づくり」だけではありません。
居心地の良さや照明、導線の設計は、席数・回転率・客単価にまで影響する「売上を左右する要素」です。
SNSで拡散される一枚の写真が、翌日の予約を埋めることだってあります。
それほど、内装デザインは集客やブランドづくりの要になっているのです。
一方で、「どんなデザインが良いのか」「どこに頼めばいいのか」「費用はどのくらいかかるのか」と悩むオーナーは多くいます。
見た目だけを重視して進めてしまい、開業後に“オペレーションが回らない”“想定よりコストがかかった”と後悔するケースも少なくありません。
この記事では、失敗しない内装デザインの決め方を、現場経験と専門家の視点からわかりやすく整理しました。
コンセプトの考え方から、業者選び、費用の目安、法規対応までを順を追って解説します。
「なんとなく決める」ではなく、「根拠を持って選ぶ」。
そんな内装づくりの第一歩を、ここから始めましょう。
なぜ内装デザインで売上が変わるのか
「雰囲気が良い店=売れる店」ではない。UX設計が利益を生む。
多くのオーナーが「おしゃれにすればお客様が来る」と考えがちですが、実際には“雰囲気の良さ”と“売上”はイコールではありません。
内装デザインで重要なのは「UX(ユーザー体験)」、つまりお客様が店で過ごす一連の体験をどう設計するかという視点です。
たとえば、初めて訪れたときに入口から席までの導線がスムーズで、メニューが見やすく、注文までの流れが自然なら、その時点で店の印象は“快適”になります。
逆に、入り口がわかりづらい、通路が狭い、席の間隔が近すぎて落ち着かない——そんな小さなストレスの積み重ねが再来店率を下げてしまうのです。
「おしゃれさ」だけを追求した空間は、体験設計が欠けると一瞬で魅力を失います。
売れる店とは、見た目ではなく“快適な導線と過ごしやすさ”で満足度を高める店です。
席数・回転率・客単価を左右する内装設計のメカニズム
飲食店経営を支える3つの指標――席数・回転率・客単価。
この3つをコントロールするのが、まさに内装設計の役割です。
例えば、席間の取り方一つで「回転率」は変わります。
テーブル間を狭くすれば席数は増えますが、居心地が悪くなり長居客が減少。
逆に広くとりすぎると滞在時間は伸びるものの、回転率が下がる。
業態によって、理想のバランスは違います。
居酒屋なら「短時間・高回転」を意識し、カフェなら「滞在価値と客単価アップ」を狙う。
どちらも“内装が数字を動かす”設計思考です。
また、照明の明るさやBGMの音量、テーブル配置なども無意識にお客様の行動を誘導します。
内装=感性+データの掛け算。
売上に強い店舗は、このバランスを意図的にデザインしています。
SNS時代のデザイン戦略:「写真に撮られる空間設計」
今の飲食店において、“写真に撮られること”はマーケティングの一部です。
SNSで拡散される空間は、「情報発信コストゼロの広告塔」。
意図的に「撮影したくなる構図」や「店の象徴になるフォーカルポイント」を仕込むことで、自然と口コミが広がります。
たとえば、カウンター奥に特徴的な照明を配置する、壁面にブランドカラーを取り入れる、席ごとに光の当たり方を変えるなど、細部の設計で印象は劇的に変わります。
見た目だけでなく、“シェアされる導線”を持つことが、現代の内装デザインの新しい基準です。
お客様がスマホを構えた瞬間、その一枚が集客の起点になる——それが今の時代の「売れる内装」です。
コンセプト設計の決め方|成功店が共通してやっている3ステップ
ペルソナ×利用シーン×業態を言語化する
成功する店舗デザインの出発点は、「どんなお客様に、どんな時間を過ごしてほしいか」を明確にすることです。
いわゆるペルソナ設定です。
例えば、同じ「カフェ」でも、ターゲットが「20代女性の一人時間」なのか、「ビジネスマンの打ち合わせ」なのかで、必要な席配置・照明・BGMはまったく異なります。
さらに、ペルソナに加えて「利用シーン」を描くことも重要です。
モーニング、ランチ、ディナー、バータイム──。
どの時間帯を主軸に置くかで、求められる照度・導線・滞在時間が変化します。
この2つを整理した上で、業態(カフェ・居酒屋・バーなど)に最適化された体験をデザインしていく。
ここをあいまいにしたまま内装を決めると、「なんとなく良いけど印象に残らない店」になってしまいます。
“誰のどんな時間を作るか”を言語化すること。
それが、デザイン以前に必要な最初の一歩です。
「ブランド体験」を内装要素(素材・色・照明)に翻訳する
ペルソナが決まったら、次はそのブランドの世界観を空間でどう表現するか。
ここで意識したいのが、「ブランド体験を物理的要素に翻訳する」ことです。
たとえば、「上質さ」なら天然木や間接照明、「開放感」なら高天井と明るいトーン、「親しみやすさ」ならファブリックや柔らかい光、という具合に、抽象的なイメージを具体的な素材・色・照明に落とし込むイメージです。
“ブランド体験=五感で感じる設計”。
内装はそのストーリーを空間で語る装置のようなものです。
この段階で、参考になる事例写真や素材サンプルを集めて「デザインボード(ムードボード)」を作っておくと、施工会社や設計士との共通認識が格段に高まります。
テイストを決める:ナチュラル/モダン/インダストリアル/和モダンなど
次に、空間の“テイスト”を決めます。
これは単なる好みではなく、ブランド戦略と客層を反映した選択です。
飲食店内装で人気のテイストは「ナチュラル(木・白を基調)」「モダン(無彩色で上質感)」「インダストリアル(コンクリート・アイアン)」「和モダン(自然素材×落ち着き)」など。
例えば、ナチュラルテイストのカフェは安心感を与え、長時間滞在に向きます。
一方、インダストリアルは非日常性を演出し、夜業態や男性客中心の店に適しています。
テイストを一つに絞るのではなく、軸を持ちながら要素をミックスすると、独自性を保ちながら印象的な空間を作ることができます。
参照事例ボード(ムードボード)の作り方
ムードボードは、内装デザインを「言葉からビジュアルに翻訳する」ためのツールです。
Pinterestなどを活用し、参考になる素材・色・照明・レイアウト・家具・装飾を集めて整理します。
ここで重要なのは、“好きなデザインを集める”のではなく、“自店の世界観に必要な要素を選ぶ”こと。
たとえば、「落ち着いた空間」を目指すなら、照度の低い照明やマットな質感の素材を、「清潔感」を重視するなら、白・木目・自然光を感じるレイアウトを。
視覚的な指針を持つことで、デザイナーや施工会社との打ち合わせがスムーズになります。
結果的に、工期短縮やコスト削減にもつながるのです。
コンセプト設計は、“最初に決めるべき経営判断”。
どんな空間にしたいかを「感覚」ではなく「言語」と「画像」で共有できるかが、プロジェクト成功の分かれ目です。
平面計画と動線設計|厨房・客席・導線の黄金比を知る
厨房と客席の理想比率:3:7が基本(ただし業態別で変動)
飲食店の平面計画でまず押さえておきたいのは、厨房と客席のバランスです。
一般的に、厨房:客席=3:7が理想とされます。
厨房が広すぎると売上を生む席数が減り、狭すぎるとオペレーションが滞る。
つまり、“利益を生む空間”と“作業を支える空間”のバランスが経営効率を決めるのです。
ただし、これは業態によって変わります。
ラーメン店や立ち食い業態などは調理スペースを広く取る傾向があり、逆にカフェや居酒屋では客席比率を高めた方が効率的な場合もあります。
厨房の形状も重要で、L字・コの字・アイランド型など、調理工程やスタッフ動線に合わせて最適化しましょう。
「厨房の設計=生産性の設計」と捉えることで、人件費の最適化や提供スピードの安定化にもつながります。
スタッフ・お客様・食材・ゴミの4動線を分ける
内装設計で意外と見落とされがちなのが、“動線の干渉”。
スタッフ、お客様、食材、ゴミ。
この4つの動線を分離することが、オペレーションの安定と衛生管理の基本です。
たとえば、客導線と配膳導線が交差していると、混雑時に衝突やストレスが発生します。
また、バックヤードへのゴミ動線が調理動線に近いと、衛生リスクが高まります。
理想は、調理→提供→片付け→清掃の流れが一方通行で完結する配置。
通路幅の目安は、スタッフ同士がすれ違える“90cm以上”。
さらに、客席導線は「入口→着席→退店」まで自然に流れる曲線構成が望ましいです。
動線のストレスが減るほど、スタッフの集中力も上がり、結果的にサービス品質も安定します。
動線が売上に直結する理由(オペ効率・滞在快適性)
動線設計は、数字に直結する内装設計の要です。
スムーズな動線はオペレーションの効率を高め、1人あたりの提供数を増やします。
結果として、同じ人員でも売上が上がる“高生産性の空間”が実現できます。
また、お客様の動線がスムーズな店ほど、滞在満足度が高い傾向にあります。
通路が狭くて人とぶつかる、トイレが見つからない、注文の声が届かない──そんな些細な不便が積み重なると、離脱率が上がってしまうのです。
飲食店における「動線設計」とは、お客様とスタッフのストレスを減らし、売上と満足度を両立させる“無形のデザイン”だといえます。
客席タイプと回転率の最適化
客席の種類と配置も、収益を左右する重要な要素です。
テーブル席・カウンター席・ボックス席・スタンディングなど、席種ごとに特徴と役割があります。
カウンターは1人客の回転率が高く、スタッフとの距離が近いためリピーターを作りやすい。
一方、テーブル席はグループ利用が中心で客単価は上がるが、滞在時間が長くなりがちです。
理想は、「高回転×高単価」の席種をバランスよく配置すること。
例えば、入口付近に回転率の高い席、奥に滞在時間が長い席を配置すると、客の流れが自然に整います。
さらに、テーブル間隔は「最低でも60cm以上」を確保すると、快適さと回転率の両立が可能です。
平面計画と動線設計は、内装の“心臓部”。
美しさよりも、まず“使いやすさ”と“効率”を設計する。
それが、長く愛される飲食店づくりの基礎です。
業態別の内装デザインポイント
飲食店の内装デザインは、業態ごとに最適解がまったく異なります。
同じ「カフェ」でも“滞在を促す店”と“回転を重視する店”では設計思想が逆。
ここでは代表的な業態別に、デザインの考え方と注意点を整理します。
カフェ:滞在時間設計・照明・電源・テイクアウト動線
カフェの内装で最も重要なのは、滞在時間と心地よさのバランス設計です。
ナチュラルな素材・柔らかい光・音量控えめのBGMは“長居したくなる空間”を作ります。
一方で、席間を広く取りすぎると回転率が下がるため、テイクアウト導線を別で設けることで全体の流れを分散させるのが理想です。
最近では、PC作業を想定して電源・Wi-Fiの位置設計も欠かせません。
また、“写真映えする1カット”を意図的に設計することが集客に直結します。
カウンター奥の照明や、ブランドロゴの入った壁など、“撮りたくなる要素”を一つ仕込んでおくのがコツです。
居酒屋:吸音・照度・掃除性・耐久性・個室比率
居酒屋のデザインでは、賑わいと快適さの両立がポイントです。
まず意識すべきは“音”。
吸音材や間仕切りを使って、声が響きすぎない環境を整えます。
照度は「テーブル上は明るく、通路は少し暗め」が黄金バランス。
視覚的な安心感とプライバシーを両立できます。
また、汚れやすい床・壁は掃除性・耐久性を重視した素材選びが必須です。
木目調シートやメラミン化粧板など、見た目の温かさと清掃のしやすさを両立させましょう。
さらに、個室や半個室の比率が高いと客単価が上がる傾向があります。
予約導線や換気ルートもあわせて検討すると理想的です。
バー:カウンター構成・照明コントラスト・音・サイン計画
バーは“空間の温度”をデザインする業態です。
特に重要なのがカウンターの構成。
バーテンダーとの距離感をどう設定するかで、店の空気が決まります。
理想的なカウンターの高さは110cm前後。
立ち・座り双方の接客が可能で、手元の演出も際立ちます。
照明は明暗のコントラストを強くすることで、非日常感を演出。
天井照度を抑え、手元とボトル棚をピンライトで照らすと効果的です。
また、音楽はBGMではなく“空気を作る要素”。
音の反響をコントロールする素材(布・木・吸音ボード)を活用しましょう。
そして、サイン(外観)設計も忘れてはいけません。
小さなバーほど、入口の光量・素材・サインの位置が“世界観を伝える最初の一手”になります。
ラーメン/中華:排気・防滑・床勾配・設備レイアウト
中華やラーメン業態では、設備と衛生が最優先です。
特に「排気」「防滑」「床勾配」は開業後のトラブルを防ぐための3大要素。
油煙が多い業態では、強力な換気ダクトとグリスフィルターが必須です。
天井高が低い場合は、排気ルートを確保できるか事前に確認しましょう。
床は油や水が飛びやすいため、防滑タイル+適切な床勾配を設けることで清掃が楽になります。
さらに、調理器具・冷蔵庫・シンクなどの設備レイアウトを“作業動線”で最適化することが重要です。
「仕込み→調理→盛り付け→提供」が一方通行になる配置を意識すると、スタッフの動きがスムーズになり、提供スピードも安定します。
業態ごとに内装の正解は違いますが、共通して言えるのは、“お客様とスタッフが心地よく動ける空間”が売上を生むということです。
美しさよりも、まずは“使いやすさと体験”を設計しましょう。
内装費用の目安と考え方【2025年最新データ付き】
坪単価相場と費用内訳(解体/造作/設備/サイン/設計料)
内装費用を考える際、最もよく使われる指標が「坪単価」です。
ただし、この数字はあくまで“目安”。店舗の状態や仕様によって大きく変動します。
2025年時点の一般的な相場は以下の通りです。
| 物件タイプ | 坪単価目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| スケルトン物件 | 40〜80万円/坪 | 一から設備・造作を行う。自由度が高いがコストも大きい。 |
| 居抜き物件 | 20〜50万円/坪 | 既存設備を活かせるため初期費用を抑えやすい。 |
| リニューアル | 15〜40万円/坪 | 既存レイアウトを生かしつつ改装。短工期で済む場合も多い。 |
主な費用の内訳は以下の通りです。
- 解体工事費:旧設備や壁の撤去など(約5〜10%)
- 造作工事費:壁・床・天井などの仕上げ(約25〜35%)
- 設備工事費:電気・給排水・空調・ガス(約30〜40%)
- サイン工事費:看板・照明・ロゴ装飾など(約5〜10%)
- 設計・デザイン料:設計士・デザイナーへの依頼費(約10〜15%)
見積書を見る際は、これらの項目ごとに費用の妥当性を確認しましょう。
特に「設備工事費」は、物件の構造や既存インフラの状態で倍以上の差が出ることもあります。
坪単価に差が出る5つの要因(仕様・工期・物件状態・申請・立地)
坪単価が変わる理由は、次の5つに集約されます。
- 仕様のグレード 素材・照明・家具の品質が高いほどコストが上がります。
- 工期の長さ 短期工事は人件費が増え、通常より10〜20%高くなることも。
- 物件状態 古い建物や設備老朽化物件は、追加工事や補修が発生しやすい。
- 申請・検査の有無 用途変更・保健所・消防などの申請費用も意外と見落とされがちです。
- 立地・階層 商業施設内やビル上層階は搬入制限があるため、工事コストが増加します。
これらを踏まえ、「坪単価だけで比較する」のではなく、条件をそろえた見積比較が必須です。
費用を抑える実践策:VE(バリューエンジニアリング)の考え方
VE(Value Engineering)とは、品質を保ちながらコストを抑える設計手法のこと。
“安くする”ではなく、“コスパを上げる”ための考え方です。
たとえば、
- 床材を本物の木材から高品質フローリングシートに変更
- 壁面装飾を減らし、照明演出で印象を作る
- 造作家具を最小限にし、既製品をカスタマイズして使う
こうした工夫で、仕上がりを損なわずに10〜20%のコスト削減が可能です。
VEの提案力が高い会社は、単なる施工業者ではなく“パートナー”として信頼できます。
居抜き物件でコストを1/3に抑えるポイント
近年人気の「居抜き物件」は、前店舗の設備や内装を再利用できるのが大きな利点です。
特に、水回り・ダクト・空調・電気容量が十分に残っている場合、
スケルトンからの開業に比べてコストを1/3以下に抑えられるケースもあります。
ただし、注意すべきは「設備の老朽化」と「用途変更の制限」。
古い配管や空調を流用すると、開業後に修繕費が発生するリスクがあります。
契約前に、必ずデザイナーまたは設備業者に現地確認を依頼しましょう。
「初期費用を抑えても、運営コストが増える」ようでは本末転倒です。
ポイントは、“安く作る”より“賢く投資する”。
内装費用は、単なる支出ではなく「回収可能な投資」。
客単価や回転率、満足度を上げる空間設計なら、数年で費用は十分に回収できます。
次章では、コスト以上に見落とされがちな「法規と申請」について解説します。
法規・申請で失敗しないために
飲食店の内装工事は、デザインや費用だけでなく、法規・申請対応も非常に重要です。
どんなに魅力的なデザインでも、法的基準を満たしていなければ営業許可が下りません。
開業スケジュールに大きく影響する部分でもあるため、設計段階から意識しておくことが大切です。
保健所:シンク数・手洗い・動線・衛生基準
飲食店営業において、保健所の許可は必須です。
特に注意が必要なのが、シンクの数と配置、手洗い場の設置。
一般的な基準として、
- 食器洗浄用の2槽シンク
- 調理器具洗浄用の1槽シンク
- 食材洗浄用のシンク
- スタッフ専用の手洗い場
といった複数の水回りが求められます。
また、「生もの」と「加熱調理品」を扱う業態では、作業台を明確に分ける必要があります。
例えば、寿司店や焼肉店では、食中毒防止のための“交差汚染対策”が最も厳しく見られるポイントです。
さらに、厨房からトイレへの導線も要注意。
直接つながっている場合はNGで、必ずドアなどで遮断することが義務づけられています。
設計前に、保健所へ「事前相談」に行くことで、後からの設計変更リスクを大幅に減らせます。
消防:内装制限・避難経路・防災設備
次に確認すべきは消防法です。
飲食店では、可燃性素材を多く使用するため、内装制限(使用できる素材の防火性能)に注意が必要です。
特に、客席面積が30㎡を超える場合は、防火仕上げの素材指定が求められることがあります。
避難経路も重要な審査項目です。
非常口が1か所しかない場合や、客席の奥まった場所から出口までの距離が長すぎると、許可が下りないことも。
スプリンクラー、誘導灯、非常照明などの防災設備は、延べ床面積や収容人数によって義務が変わります。
デザイナー任せにせず、着工前に消防署へ図面相談を行うのが鉄則です。
建築基準・用途変更・インフラ容量(電気/ガス/排水)
意外と見落とされるのが、建築基準法とインフラ容量の確認です。
特に注意したいのが「用途変更」。
元がオフィスや物販店舗だった物件を飲食店に改装する場合、建築基準法上の用途変更申請が必要になるケースがあります。
また、飲食店は一般店舗よりも電気・ガス・排水の負荷が大きいため、
- 電気容量(目安:20〜30kW以上)
- ガス圧・供給量(業務用コンロ・給湯器分)
- 排水能力(油脂分離槽の設置有無)
などを事前に確認しておきましょう。
これらを軽視してしまうと、「電圧不足で機器が動かない」「排水が詰まる」「検査が通らない」といったトラブルにつながります。
法規対応は、工事前に“相談”することが何よりの近道。
保健所・消防署・建築指導課――。
どの機関も、事前に図面を見せれば丁寧にアドバイスしてくれます。
“デザインを描いてから確認”ではなく、“法規を踏まえてデザインを描く”。
これが、開業スケジュールを守る最も確実な方法です。
次章では、実際にデザイン会社を選び、発注する際の判断基準を解説します。
内装デザイン会社の選び方と発注方法
内装の成功を左右する最大の要因――それが「誰に依頼するか」です。
同じ図面でも、デザイン会社や施工業者の力量次第で、仕上がり・コスト・スケジュールは大きく変わります。
ここでは、失敗しないパートナー選びのポイントを整理します。
設計施工一括 vs 設計監理分離(メリット・デメリット)
まずは、発注形態を理解しましょう。
- 設計施工一括型 デザインから施工までを1社が一貫して担当する方式です。 メリットは、スピードとコストの明確さ。 1社に任せるため打ち合わせが少なく、見積もりや工期も比較的スムーズに進みます。 ただし、デザイン・コスト・品質のチェックが一体化しているため、第三者視点の監理が入りにくい点がデメリットです。
- 設計監理分離型 設計(デザイン)と施工を別会社に依頼する方式です。 メリットは、見積りの透明性と品質管理。 デザイナーが監理者として現場をチェックするため、仕上がりの精度が高くなります。 デメリットは、工期がやや長く、初期コストが上がりやすいこと。
短期間・小規模リニューアルなら「設計施工一括」、
ブランド構築や複数店舗展開を見据えるなら「設計監理分離」が向いています。
会社選定の3基準:実績業態・見積透明性・現場監理体制
デザイン会社を選ぶ際は、以下の3点をチェックしてください。
- 実績業態が自店と近いか 同じ「飲食店」でも、カフェと焼肉店では設計思想がまったく違います。 自分の業態に近い施工実績を持つ会社は、厨房動線や法規対応にも強いです。
- 見積の透明性があるか 「坪単価だけ提示」「詳細項目なし」は要注意。 工事項目を細かく分けた内訳書付き見積を出してくれる会社は信頼できます。
- 現場監理体制が明確か デザイナーが現場をどの頻度で確認するか、工事責任者が誰かを事前に確認しましょう。 トラブルの多くは「監理の不在」が原因です。
相見積もりの取り方&比較チェックリスト
内装費用を適正に抑えるには、最低3社の相見積もりを取るのが鉄則です。
比較の際は「金額の安さ」だけでなく、次の項目をチェックしましょう。
- 工事項目の抜け漏れがないか
- 設備工事費が極端に安く(または高く)ないか
- 納期の現実性(工期が短すぎないか)
- アフターメンテナンス・保証内容があるか
同じ仕様で比較するためには、RFP(依頼書)や仕様書を自店で用意すると理想的です。
契約書で必ず確認すべき項目(支払い/工期遅延/瑕疵保証/著作権)
最後に、契約時の注意点です。
- 支払い条件 着手金・中間金・残金のタイミングを明確に。 「完成後の支払い割合」が少なすぎる契約は避けましょう。
- 工期遅延時の取り決め 遅延理由と補償範囲を明文化しておくとトラブルを防げます。
- 瑕疵保証期間 引渡し後の不具合(照明・床・排水など)に対する保証期間を確認。 一般的には1年が目安です。
- 著作権の扱い デザイン図面の著作権は誰に帰属するかを契約前に確認。 自店で再利用する可能性がある場合は、使用許諾を明記しましょう。
デザイン会社の選定は、「金額」よりも「信頼関係」。
一緒に“お店をつくる”パートナーとして、レスポンス・提案力・誠実さを見極めましょう。
次章では、実際の現場で起きやすい「内装トラブルとその回避策」を紹介します。
よくある失敗と回避策【実例付き】
内装デザインは、完成してから「こうすれば良かった」と気づくことが多い分野です。
ここでは、実際の飲食店で起きやすい失敗例をもとに、原因と防止策を具体的に解説します。
匂い・排気トラブル(ダクトルート/上階クレーム)
飲食店トラブルで最も多いのが「匂い問題」です。
特に焼肉・中華・揚げ物業態では、排気の設計を軽視すると致命的。
例えば、上階の住居に臭気が漏れたり、隣店舗の吸気口とダクト位置が近くて苦情が出るケースもあります。
対策ポイント:
- ダクトのルートは「屋上排気」または「高所排気」を基本とする。
- 消臭フィルターやグリスフィルターを設置し、清掃頻度を明確にする。
- 排気経路を決める前に、ビルオーナーと管理会社へ事前確認を行う。
特に都心のテナントビルでは、排気ルートが限られることが多く、「物件契約前のチェック」が最も重要です。
オペレーション動線が詰まる(厨房→客席→バックヤード)
「デザインは良いのに、使いづらい店」という声の多くは、動線設計のミスから生まれます。
厨房から客席までの通路が狭く、配膳中にスタッフ同士がぶつかる。
バックヤードが遠く、補充や片付けに時間がかかる。
こうした「1歩多い」構造は、日々の業務効率を確実に下げます。
回避策:
- 料理の出入口を2箇所設ける(出す導線と戻る導線を分ける)
- 客席通路は最低90cm、厨房通路は120cmを確保
- スタッフの動きを実際にシミュレーションしながら配置を決める
動線が整うだけで、同じ人員でも1.2〜1.5倍の提供効率を生むこともあります。
素材選定ミスで清掃性・耐久性に難あり
オープン直後は美しくても、半年後に「床が黒ずむ」「壁が汚れやすい」「カウンターが傷だらけ」といった問題が発生するのもよくある話です。
原因は、素材選びの優先順位を“見た目”に置いてしまうこと。
特に注意すべきは以下の3点。
- 床材:水や油を扱う業態では、防滑性+耐薬品性のある素材を選ぶ。
- 壁材:吸湿しやすい素材(珪藻土など)は、水回りに不向き。
- カウンター:木無垢材は風合いが良いが、コーティングがないと汚れが染みやすい。
- 「デザイン性×清掃性×耐久性」の3条件を満たす素材を選ぶことが、長期的には最もコスパの良い選択です。
“映える”が目的化してブランディングが崩壊
SNS時代の飲食店にありがちな落とし穴が、「映える内装を狙いすぎる」こと。
たしかに、SNSで話題になるようなデザインは集客効果があります。
しかし、空間がブランドコンセプトとズレてしまうと、リピート率が激減します。
例えば、“禅の静けさ”をテーマにしたカフェが、ネオンライトや派手な装飾を取り入れてしまうと、ブランドメッセージがぼやけてしまいます。
回避策:
- 「SNS映え」はあくまで“結果”であり、“目的”ではない。
- コンセプト→体験→写真映え、の順で考える。
- 写真映えを狙うなら、空間全体より「1カットの象徴」を設ける。
“写真に撮られる空間”は、ブランド体験と一貫していることが大前提です。
どんな店舗でも、「デザイン」「動線」「素材」「ブランド表現」のどれかを疎かにすると、必ず運営に影響が出ます。
内装の失敗はデザインミスではなく、“決定の順番ミス”から生まれる。
この視点を持つだけで、ほとんどのトラブルは未然に防げます。
次章では、より長期的な視点で考える「サステナブルな内装設計」について解説します。
サステナブル&長期運用のためのデザイン視点
内装デザインを考えるうえで、最近ますます重要視されているのがサステナブルな設計です。
開業時のコストだけでなく、「5年後」「10年後」も快適に運用できるかどうか。
つまり、ライフサイクル全体を見据えたデザインが、これからのスタンダードです。
長寿命素材/再利用可能什器/補修性の高い仕上げ
「長く持たせる」という視点で見ると、まず注目すべきは素材選びです。
例えば、壁紙よりも塗装仕上げにすることで、汚れや剥がれが出ても部分補修がしやすくなります。
床材も、無垢フローリングではなく張り替え可能なタイルや塩ビタイルを採用すれば、リニューアル時の廃棄物を減らせます。
また、什器や家具を固定造作にしすぎないこともポイント。
可動式テーブルや モジュラー家具を導入すれば、レイアウト変更やイベント対応が柔軟にでき、結果的に長期的なコスト削減につながります。
店舗は一度作って終わりではなく、“育てる空間”。
そのために「修理しやすい」「入れ替えやすい」構造を意識しましょう。
省エネ照明・空調とLCC(ライフサイクルコスト)
サステナブルデザインのもう一つの柱が、エネルギー効率です。
初期費用はやや高くても、LED照明や高効率エアコンなどを導入することで、光熱費を年間で15〜30%削減できる場合があります。
また、照明は「照度コントロール」を設計段階から組み込むのがおすすめです。
昼夜で明るさを調整できる調光システムを導入すれば、雰囲気の演出と省エネを両立できます。
さらに、空調の吹き出し位置や排気ルートも、快適さと省エネの両方を左右するポイントです。
定期的なフィルター清掃や風量バランスの調整で、稼働効率を維持しましょう。
サステナブルとは「地球にやさしい」だけでなく、“店舗経営にもやさしい”ということ。
LCC(ライフサイクルコスト)を意識すれば、長く愛される店を持続可能な形で運営できます。
グリーン内装・地域素材の活用(SDGs対応店舗の潮流)
最近では、インテリアの一部にグリーン(植物)や地域素材を取り入れる店舗が増えています。
観葉植物を配置するだけで、心理的な安心感が高まり、ストレス軽減効果が期待できます。
また、地域の木材や左官素材を使うことで、地域ブランドとの結びつきやストーリー性を強化できます。
こうした取り組みは、SDGsの観点からも評価されやすく、行政補助金やメディア露出のきっかけになることもあります。
特に最近では、環境配慮×デザイン性を両立した「エシカル店舗」が増加傾向です。
環境意識の高い若年層や企業コラボにもつながる可能性があり、ブランディング面でも大きな価値を持ちます。
サステナブルな設計とは、“流行を超えて続く空間”をつくること。
壊すことを前提にするのではなく、直して使い続ける発想を持つことで、
コスト・環境・ブランドのすべてを豊かにできます。
次章では、開業までのスケジュールと、オーナーが確認すべきチェックリストを解説します。
開業までのスケジュールとチェックリスト
内装デザインを成功させるには、“正しい順番で決めていく”ことが何より大切です。
デザインの善し悪しはもちろんですが、スケジュール管理を誤ると「オープンに間に合わない」「許可が取れない」といった致命的な問題につながります。
ここでは、開業までの一般的な流れと、各フェーズでやるべきことを整理します。
開業標準スケジュール(物件契約→設計→工事→引渡)
飲食店の内装工事は、規模や物件状況によって変わりますが、一般的には2〜3か月が目安です。
以下は、スケルトン物件を想定した標準的な流れです。
| フェーズ | 主な内容 | 期間目安 |
|---|---|---|
| ① 物件契約前 | 物件調査・排気/電気容量確認・法規リスク確認 | 約1〜2週間 |
| ② 基本設計 | コンセプト設計・平面レイアウト作成・概算見積 | 約2〜3週間 |
| ③ 実施設計 | 詳細図面作成・設備仕様決定・見積確定 | 約2週間 |
| ④ 申請期間 | 保健所・消防・建築関連の事前申請 | 約1〜2週間 |
| ⑤ 工事期間 | 解体→造作→設備→仕上げ→クリーニング | 約4〜6週間 |
| ⑥ 引渡・検査 | 試運転・不具合チェック・営業許可申請 | 約1週間 |
スケジュールが詰まりやすいのは「申請」と「設備工事」です。
特に新築ビルや居抜き再利用の場合、排気ダクト・給排水経路の確認に時間がかかることを想定しておきましょう。
各フェーズでやるべきこと(許可申請/見積承認/工事監理)
物件契約前
- ダクトルート・電気容量・ガス圧を現地確認
- 居抜きの場合は既存設備の劣化チェック
- 用途変更の有無を建築指導課に相談
設計期間
- デザイン会社と“予算上限”を明確に共有
- 施工会社から概算見積を取得
- 設計内容を保健所に事前相談しておく
施工期間
- 工事中は週1回以上の現場確認を行う
- 追加工事が発生した場合は必ず書面で承認
- 設備試運転・照明チェック・清掃確認
引渡前
- 壁や床の傷・仕上がり確認(是正リスト作成)
- 水漏れ・ガス漏れ・電気容量の確認
- 保健所の営業許可検査に立ち会う
オーナー用チェックリスト
□ コンセプト設計が明確になっている
□ 平面図と動線図を見てオペレーションを再現できる
□ 見積内訳書が詳細に提示されている
□ 申請書類(保健所・消防)を提出済み
□ 設備容量(電気・ガス・排水)を確認済み
□ 現場監理の担当者と連絡が取れる体制を構築
□ 工事完了前に是正チェックを行った
□ 営業許可・開業届など行政手続きが完了している
このように、内装プロジェクトは「確認の積み重ね」で成功が決まります。
工事そのものよりも、オーナーの意思決定スピードと情報整理力がプロジェクトを左右します。
内装は“作る”だけでなく、“管理する”もの。
スケジュールを味方につけることで、予算・品質・納期をすべて最適化できます。
次章では、開業準備時によく寄せられる質問をまとめて解説します。
FAQ(よくある質問)
Q1. 内装費用を最小限に抑えるには?
まず意識すべきは、「安く作る」ではなく「ムダを省く」という発想です。
費用を抑える具体的な方法としては、
- 居抜き物件を活用する(水回りや空調を再利用できる)
- 仕上げ素材のグレードを調整する(壁紙や床材を代替素材に)
- 造作家具を減らして既製品をカスタマイズする
- VE(バリューエンジニアリング)を意識する(デザイン性を保ちながらコスト最適化)
また、業者と打ち合わせの際に「どこまでコストを下げたいか」を明確に伝えることで、
提案内容の精度も上がります。
Q2. 相見積は何社がベスト?
理想は3社です。
2社だと比較の幅が狭く、4社以上になると調整が煩雑になりがちです。
同じ図面・条件で見積を依頼し、金額だけでなく“抜け漏れ”や“対応スピード”も比較基準に入れましょう。
また、「最安値の会社」よりも、「説明が丁寧な会社」を選ぶのが結果的に満足度を高めます。
Q3. 居抜きとスケルトン、どちらが得?
初期コストを抑えたいなら、居抜き物件が有利です。
既存設備を活用できるため、スケルトンよりも最大で1/2〜1/3のコストで開業できる場合があります。
ただし、古い設備を流用すると修繕費が発生することもあるため、
契約前に設備状態をプロにチェックしてもらうことが大切です。
一方、ブランドの世界観を一から作りたい、または特殊な業態(焙煎所・ライブバーなど)の場合は、
スケルトンの方が自由度が高く、結果的に理想の店舗が作りやすくなります。
Q4. デザイン会社と工務店、どちらに依頼すべき?
結論から言えば、店舗の規模と目的によって使い分けるのがベストです。
- 小規模店/スピード重視 → 設計施工一括の工務店が効率的。
- ブランド構築/複数展開予定 → デザイン会社に依頼して監理付きで進めるのが安心。
工務店はコストパフォーマンスが高い一方、
デザイン会社は世界観やブランディングの表現力に優れています。
- 「誰に任せるか」より、「どんな目的で任せるか」を明確にすることが最も大切です。
飲食店の内装は、正解が一つではありません。
しかし、目的・予算・業者の強みを整理すれば、ほとんどの失敗は防げます。
次章では、本記事全体のまとめとして、失敗しない内装デザインの決定プロセスを振り返ります。
まとめ|失敗しないための決定プロセスを体系化しよう
飲食店の内装デザインは、感覚だけで決めるものではありません。
成功している店舗には、必ず「正しい順番」と「判断基準」があります。
コンセプト → 平面 → 業者 → 法規 → 費用管理 → 工事監理
- コンセプト設計: 誰にどんな時間を過ごしてもらうかを明確にし、世界観を言語化する。
- 平面計画・動線設計: スタッフとお客様がスムーズに動ける導線を整え、効率と快適さを両立する。
- 業者選定: 実績・見積の透明性・監理体制を軸に、信頼できるパートナーを選ぶ。
- 法規対応: 保健所・消防・建築基準を事前に確認し、設計段階からクリアにしておく。
- 費用管理: VE(バリューエンジニアリング)で品質を保ちながらコスト最適化。
- 工事監理: 現場を定期チェックし、仕上がり・スケジュール・追加費用を徹底管理する。
“内装=投資”という発想を持つ
内装費用は支出ではなく、未来への投資です。
ブランドを体現する空間があれば、リピート率が上がり、スタッフのモチベーションも向上します。
逆に、「安く早く仕上げる」ことだけを優先すると、必ず後から修繕費や機会損失という形で返ってきます。
大切なのは、最初に何を優先すべきかを決めること。
その優先順位こそが、あなたのブランドの価値を決定づけます。
次アクション
- ✅ オーナー用チェックリストを活用し、現状を整理する
- ✅ デザイン会社・施工会社を3社比較して見積を確認する
- ✅ 平面図・動線計画を基に、実際の導線をシミュレーションしてみる
内装は「最初の意思決定」で勝負の8割が決まります。
感覚だけで進めず、ロジックと経験を持って設計すれば、開業後の景色はまるで違うものになります。
あなたの理想の店舗が、長く愛される場所になりますように。