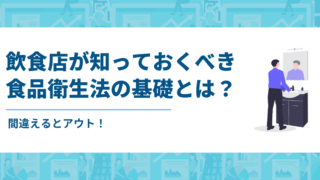1. 食品を輸入するには「届出」が必要!その理由とは?
食品輸入時に求められる届出とは?
「海外の魅力的な食品を日本で販売したい」「個人輸入で食品を取り寄せたい」。そんなとき、まず立ちはだかるのが「食品等輸入届出書」という手続きです。
この届出は、すべての食品輸入者が避けては通れない必須のステップ。税関を通過する前に、厚生労働省の所管である検疫所へ書類を提出しなければなりません。
なぜ届出が必要かというと、日本の食品安全基準に合致しているかどうかを輸入時点で確認するためです。つまり、国内の消費者を守るための「食の安全網」の一環。輸入者としては、「何を」「どこから」「どのように」持ち込むかを正確に申告する義務があります。
では、なぜそこまで厳しくチェックされるのでしょうか?次の項で詳しく解説していきます。
食品衛生法に基づく届出制度の概要
「食品等輸入届出書」の根拠は、食品衛生法第27条にあります。この法律は、国民の健康を守るために、国内外すべての食品の安全性を確保することを目的としています。
具体的には、以下のような事項がチェックされます:
- 使用されている原材料に有害なものがないか
- 殺菌・加熱処理が適切に行われているか
- 添加物の使用が日本の基準に合っているか
- 梱包・保管方法が衛生的か
また、届出を出すだけではなく、検疫所が必要と判断すれば、サンプル検査が実施されることも。たとえば、残留農薬の有無や、細菌の検出など、安全性に関わるチェックが入ります。
これにより、私たち消費者は、海外の食品を安心して口にできるのです。
届出をしないとどうなる?リスクと罰則
「面倒だし、出さなくてもバレないのでは?」と思ったあなた。絶対にやめましょう。
食品等輸入届出書を提出しないで輸入した場合、それは違法行為にあたります。
以下のようなリスクがあります:
- 税関で止められる
- 食品が廃棄処分される
- 再発防止の指導を受ける
- 悪質な場合、業務停止命令や刑事罰の対象になる
特に法人として継続的に輸入を行う場合、信頼を損なえば取引先や顧客からの信用も失われます。
一方で、正しく届出を行えば、スムーズな通関・販売につながります。信頼できるビジネスの基盤をつくるためにも、届出の手続きは「コスト」ではなく「投資」と考えるべきでしょう。
2.「食品等輸入届出書」とは?役割と必要性を理解しよう
食品等輸入届出書の目的
「食品等輸入届出書」は、海外から日本に食品を持ち込む際に必ず提出すべき書類です。では、この書類にはどんな役割があるのでしょうか?
その最大の目的は、日本国内に流通させる食品が、食品衛生法に適合しているかを事前に確認することです。つまり、「安全な食品かどうか」をチェックする入口なのです。
特に日本は、添加物や残留農薬、微生物の基準が世界でも非常に厳しい国。そのため、食品の製造国で「安全」とされている食品でも、日本の基準には合わない場合があります。
この届出書を通じて、検疫所の担当者は以下のような情報を確認します:
- 食品の種類・製造方法
- 原材料や添加物の詳細
- 加熱処理や保存方法
- 製造工場や流通経路の管理体制
このように、「食品等輸入届出書」はただの書類ではなく、日本の食品安全を守る大切なフィルターのような存在なのです。
提出が必要なケースと不要なケース
「すべての食品に届出が必要なの?」という質問をよく耳にします。実は、すべてのケースで必要とは限りません。以下に簡単に分類してみましょう。
✅ 提出が必要なケース
- 商業目的で輸入する食品・添加物・容器包装
- 店舗やECで販売予定の商品
- 他人に提供するための輸入(例:レストラン、カフェ)
❌ 提出が不要なケース(一部)
- 個人が自分で食べるためにごく少量輸入する場合
- サンプルとして輸入するが販売しない場合(ただし検査の対象になることも)
- すでに国内で製造・販売実績があり、特定条件を満たす商品(※要確認)
ただし、提出が不要なケースでも、税関で質問されることがあるため、証明できる書類を用意しておくのが安全策です。
「これって届出必要?」と迷ったときは、最寄りの検疫所や行政書士など専門家に相談するとスムーズです。
対象となる食品・添加物・容器包装とは
「食品等輸入届出書」は、実は食品そのものだけでなく、“関連するすべてのもの”に適用されます。以下の3カテゴリーが主な対象です。
1. 食品
加工食品(クッキー、缶詰、レトルト食品など)、生鮮食品(野菜、肉、魚)、冷凍食品などが含まれます。
2. 添加物
甘味料、保存料、着色料など。日本で使用が許可されていない添加物が含まれていると、輸入できません。
3. 器具・容器包装
食品に接触する可能性のあるものも対象です。プラスチック容器やパッケージ、カトラリーなどが該当します。
ポイントは、「食べ物そのもの」以外でも、食品と接触する可能性があるものは対象になるという点。思わぬ落とし穴があるので、しっかりと事前確認をしておくことが重要です。
3. 食品等輸入届出書の正しい書き方【記入例あり】
書類の構成と必要な情報
食品等輸入届出書は、検疫所に提出する正式な行政文書です。書き方を間違えると、差し戻しや審査遅延の原因になります。まずは、書類の基本構成を確認しましょう。
主な記載項目は以下の通りです:
- 輸入者情報:会社名、所在地、担当者連絡先など
- 輸入食品の詳細:商品名、種類、加工の有無、用途
- 製造工場情報:工場名、所在地、管理体制など
- 成分・原材料情報:食品添加物や栄養成分などの内訳
- 輸送・保存方法:冷蔵・冷凍・常温など
- 容器包装の材質・構造:プラスチックかガラスか、内袋の有無など
これらはFAINS(輸入食品監視支援システム)を使った電子申請でも、紙ベースの提出でも基本的に同じです。
書類は正確性が命です。事前にインボイスや仕様書などの関連書類を揃え、一つ一つの項目を丁寧に確認して記入しましょう。
よくある記入ミスとその対処法
届出書でよく見られるミスには、いくつかの“パターン”があります。以下は、検疫所でよく指摘されるポイントです:
- 原材料の記載漏れ
→ 使用している材料をすべて明記。特にアレルゲン成分の記載は要注意です。 - 製造工程が不明確
→ 加熱の有無、殺菌工程など、安全性に関わる情報は詳細に書きましょう。 - 容器包装の記述不足
→「プラスチック容器」だけでなく、“内袋の有無”、“密封状態”なども明記。 - 英語だけで書いてしまう
→ 届出書は基本的に日本語記載が必要。英語表記しかない場合は翻訳を添付。 - 製造国・工場の情報が不正確
→ 工場が複数ある場合は、それぞれの情報を正確に記載しましょう。
これらのミスを避けるためにも、事前に検疫所のチェックリストやガイドラインを確認しておくことが重要です。また、初めての届出なら行政書士に相談するのも選択肢です。
記入例付きでわかりやすく解説
以下は、実際の記入例(※簡略版)です。
【輸入者情報】
会社名:株式会社グローバルフーズ
所在地:東京都港区〇〇1-2-3
担当者名:山田 太郎
電話番号:03-1234-5678
【食品の詳細】
商品名:チョコレートクッキー(Chocolate Cookies)
分類:加工食品(焼菓子)
原材料:小麦粉、砂糖、バター、卵、カカオパウダー、ベーキングパウダー
アレルゲン:小麦、卵、乳
【製造工場】
名称:Sweet Factory Ltd.
所在地:アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス
【保存方法】
常温(25℃以下)
【容器包装】
外装:紙箱
内装:ポリプロピレン袋(密封)
ポイントは、できるだけ正確かつ具体的に書くことです。検疫所の担当者が見て「不明点がない」と判断できるように書くのが理想です。
このような記入例を参考に、自社商品に合わせてカスタマイズしていきましょう。
4. 食品等輸入届出書の提出方法と提出先一覧【全国対応】
提出先:検疫所(輸入先の地域ごとに)
食品等輸入届出書の提出先は、**「輸入貨物が到着する港や空港を管轄する検疫所」**です。例えば、成田空港に到着する場合は「成田空港検疫所」、横浜港なら「横浜検疫所」といった具合です。
提出前に、自社の貨物がどこの港・空港に届くのかを必ず確認しましょう。地域別に主な検疫所を以下に示します。
| 地域 | 主な検疫所名 |
|---|---|
| 関東 | 東京検疫所、成田空港検疫所、横浜検疫所 |
| 関西 | 大阪検疫所、関西空港検疫所、神戸検疫所 |
| 九州 | 福岡検疫所、博多港支所、那覇検疫所 |
| 中部 | 名古屋検疫所、静岡検疫所 |
| 北海道・東北 | 札幌検疫所、仙台検疫所 |
検疫所の所在地や連絡先は、厚生労働省の公式ページから最新情報を確認できます。事前に電話で相談できる場合も多く、初回は直接相談するのが安心です。
電子申請(FAINS)の利用方法と登録手順
最近は、書面での提出だけでなく、オンラインによる「電子申請(FAINS)」も利用できます。
FAINS(輸入食品監視支援システム)は、厚生労働省が提供する公式のオンライン届出システムです。
🔸FAINSの主なメリット:
- 24時間いつでも申請可能
- 書類の提出がスピーディーに
- 過去の届出履歴を確認できる
- 添付書類のアップロードも可能
🖥 FAINS利用のステップ:
- 利用者登録(厚労省のサイトでアカウント開設)
- ログイン後、申請フォーム入力
- 必要書類をPDF等で添付
- 提出ボタンをクリックし、完了通知を待つ
登録には、法人番号や輸入者情報の入力が必要です。申請は日本語で行うため、外国企業が利用する場合は日本側代理人のサポートが必要になります。
※FAINSについての公式案内ページはこちら(厚生労働省):
👉 FAINSシステムガイド(厚労省)
書面提出との違いと注意点
電子申請が便利とはいえ、すべての申請が完全にオンラインで完結するわけではありません。以下のような点に注意が必要です。
書面提出が必要になるケース:
- 初めて輸入する商品で、詳細確認が必要な場合
- 電子データで確認できない検査証明書類がある場合
- FAINS利用が困難な個人や小規模業者
また、電子申請であっても、検疫所から追加資料の提出を求められることがあります。
その際は、書面での補足提出が必要になることも。
さらに、FAINSでの届出完了後も、税関への通関手続きとは別になるので注意しましょう。輸入業務は複数の省庁にまたがるため、物流担当者や通関士との連携が重要です。
5. 提出後の流れと審査のポイント
届出後に行われる内容審査と必要書類の確認
食品等輸入届出書を提出したあと、検疫所ではただ受け取るだけではありません。ここから始まるのが、「内容審査」です。
提出された情報に不備がないか、輸入食品が日本の基準に適合しているかを、書類ベースで詳細にチェックします。審査では、以下のようなポイントが見られます:
- 成分や製造工程が安全性基準に適しているか
- 使用されている添加物が日本で許可されているか
- 製造工場が衛生的に管理されているか
- 製品が適切に加熱処理されているか(特に動物性食品)
さらに、商品や輸入ルートによっては検査対象となることもあります。その場合、実際にサンプルを提出して、微生物検査や成分検査を受けることになります。
審査にかかる時間と注意点
審査にかかる期間は、通常1~3営業日程度が目安です。
ただし、以下のような場合は5~7日、またはそれ以上かかることもあります。
- 初めての輸入で、製品情報が不十分
- 高リスク食品(生鮮肉類、乳製品、蜂蜜など)
- 海外の新興メーカーからの輸入で、実績がない
- 提出書類に不備・記載漏れがある
一番避けたいのは、「記入ミスや不備による差し戻し」です。再提出となると、物流のスケジュールに大きな影響を与えかねません。
事前に製品仕様書(スペックシート)や、製造証明書、衛生管理証明などを整えておくと、審査がスムーズに進みます。
修正・差し戻し対応の仕方
万が一、届出が差し戻された場合、慌てずに冷静に対応しましょう。
検疫所からは、具体的な差し戻し理由が通知されるため、指示に沿って以下のステップで進めます。
🔧 差し戻し対応の基本ステップ
- 通知内容を確認(メールまたはFAINS内で確認可能)
- 指摘された項目の修正、または追加資料の準備
- 修正した届出書を再提出(電子 or 書面)
- 再審査が行われ、問題なければ「届出済証」が発行される
修正依頼が来た場合は、できるだけ迅速に対応することがポイントです。再提出が遅れると、その分通関も遅れてしまい、納品遅延やコスト増に直結します。
また、複雑な差し戻し内容や専門的な指摘が多い場合は、食品衛生法に詳しい行政書士に依頼するのも一つの手段です。スピードと確実性の両方を確保できます。
6. 食品輸入のよくある質問【Q&A】
少量・個人利用でも届出が必要?
結論から言うと、「個人が自分で食べるため」に少量輸入する場合は、基本的に届出は不要です。
しかし、以下のようなケースでは注意が必要です:
- 量が多すぎる(商業利用と疑われる)
- 他人に提供する予定がある(おすそ分け含む)
- 販売サイトなどでの転売が疑われる
また、個人輸入であっても、特定の品目(例:生肉・乳製品・ハチミツなど)は、届出や検査が必要な場合があります。輸入前に必ず、厚生労働省のガイドラインや検疫所に確認しておきましょう。
海外OEM商品の場合はどうなる?
最近増えているのが、海外で製造されたOEM(プライベートブランド)商品を日本で販売するケースです。これは立派な「食品の輸入」に該当します。
OEM商品でも以下の手続きが必要です:
- 食品等輸入届出書の提出
- 製造工場の情報開示(安全管理体制の確認)
- 商品ラベルの日本語表記(食品表示法に基づく)
特に気をつけたいのは、製造工場のトレーサビリティ(追跡性)です。
たとえパッケージに自社ブランド名が記載されていても、製造元や製造工程の情報が不十分だと、届出が受理されない可能性があります。
また、OEM商品は一見「自社商品」のように見えますが、輸入元の責任は100%自社にあるということを忘れずに。食品表示や衛生管理、万が一の事故への対応も含め、しっかりと体制を整えておきましょう。
届出書の有効期限や保管義務はある?
食品等輸入届出書そのものには、有効期限はありません。ただし、輸入のたびに毎回提出が必要です。
つまり、「同じ商品を定期的に輸入する場合」でも、都度、新たに届出が求められるということです(ただし一部簡略化手続きが可能なケースもあります)。
また、提出した届出書や関連資料については、一定期間保管する義務があります。明確な保管期間は定められていないものの、厚労省では最低2年間の保管を推奨しています。
さらに、食品事故が発生した場合などには、過去の届出内容や輸入記録が求められることもありますので、データはクラウドや紙でしっかり管理しておきましょう。
7. まとめ|食品等輸入届出書の提出は、確実かつ正確に!
記事のおさらいと注意点の再確認
ここまで、「食品等輸入届出書」について、その必要性・書き方・提出先・審査の流れなどを詳しく解説してきました。
最後に、ポイントを簡単に振り返ってみましょう:
- 食品を海外から輸入するには届出が必須
- 食品衛生法に基づき、安全性を担保するための制度
- 届出書の記入には、正確で詳細な情報が求められる
- 提出は検疫所またはFAINSによる電子申請が可能
- 審査に備えて、必要書類は事前にしっかり準備を
そして何より大切なのは、「適当には済ませられない手続き」であるという意識です。
一度のミスが、物流の遅延や販売停止など、ビジネス上の大きな損失に直結する可能性もあります。
専門家や行政書士に依頼するのはアリ?
「手続きが難しそう」「海外メーカーとのやり取りもあるし不安…」
そんな方には、食品輸入に詳しい行政書士や通関士に相談・依頼するのも有効です。
プロに任せることで:
- 記載ミスや不備のリスクを回避
- 複雑な書類の準備がスムーズに
- 審査や検査がスピーディに進む可能性が高まる
特に、初めて輸入を行う場合や、商品数が多い場合には強い味方になります。
もちろん、自社で対応することも可能です。ただし、しっかりと事前準備をし、検疫所や厚労省のガイドラインを熟読することを忘れずに。