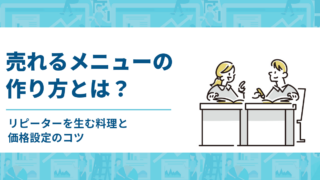「どのメニューを残し、どれを削るべきか」――。
多くの飲食店オーナーが抱える悩みのひとつです。売上は悪くないのに利益が思うように残らない。
人気メニューに原価がかかりすぎている。そんな“勘と経験頼りの経営”から抜け出すには、数字の力が欠かせません。
その鍵となるのが「ABC分析」です。
ABC分析とは、メニューや商品を売上・利益などの貢献度によってA・B・Cの3ランクに分類し、店舗の稼ぎ頭と足を引っ張る要因を見える化する方法。
経営判断の軸を「感覚」から「データ」に変えることができます。
本記事では、単なる売上分析にとどまらず、粗利率・在庫・人件費を含めた“利益を最大化するABC分析” を実践的に解説します。
さらにカフェ・居酒屋・レストランなど業態別の事例、Excelテンプレート、最新ツールまで紹介。
あなたの店舗の「数字」を、今日から意思決定の武器にしていきましょう。
ABC分析とは?|メニューごとの貢献度を「見える化」する手法
ABC分析の基本定義と目的
ABC分析とは、商品やメニューを売上・数量・粗利の貢献度ごとにA・B・Cの3つのランクに分類する分析手法です。
もともとは製造業や物流分野で在庫管理に使われていた考え方ですが、近年は飲食業でも「データ経営」の基本として広く活用されています。
目的はシンプル。
「何が店の利益を支えているのか」を数値で明確にし、重点的に管理・改善すべき対象を見える化することです。
| ランク | 特徴 | 売上構成比の目安 | 経営判断の方向性 |
|---|---|---|---|
| Aランク | 店の利益を支える主力商品 | 上位70〜80% | 品質維持・安定供給を最優先 |
| Bランク | 成長余地のある準主力 | 次の15〜25% | 改良・販促でAランク昇格を狙う |
| Cランク | 売上貢献が低い商品 | 下位5〜10% | 廃止・改善・入れ替えを検討 |
たとえば、ドリンクメニューで「A=コーヒー、B=紅茶、C=スムージー」と分類されたとします。
このときAのコーヒーは安定供給を重視し、Bの紅茶は販促強化、Cのスムージーは原価や在庫を見直す――このように、メニューごとの“打ち手”が明確になります。
ABC分析は、単なる「数字の分類」ではありません。
売上データを利益戦略に変える“意思決定ツール”として、日々のメニュー構成や仕入れ判断に活用できるのが最大の特徴です。
「売上ベース」だけでは見えない落とし穴
多くの飲食店が最初に行うのは「売上金額」を基準にしたABC分析です。
もちろん悪くはありませんが、売上だけでは真の利益構造を見誤ることがあります。
たとえば、
- Aランク:人気だが原価が高く、粗利がほとんど残らないメニュー
- Bランク:販売数は少ないが粗利率が高く、実は利益貢献が大きいメニュー
このようなケースでは、売上ベースの分析だけでは「本当に稼げる商品」を見逃してしまうのです。
そこで活用したいのが、粗利ベースのABC分析。
各商品の「売上 − 原価」=粗利額を算出し、それを基準にランクをつけることで、“売れているだけのメニュー”と“利益を生むメニュー”を区別できます。
実際、繁盛店の多くは売上よりも「粗利構成比」で管理しています。
「売上は見せかけ、粗利は真実」と言われるように、利益を最大化するには、どの商品が本当の稼ぎ頭なのかを明確にする視点が欠かせません。
飲食店でABC分析を行う3つのメリット
ABC分析は、単にメニューをランク分けするだけの作業ではありません。
店舗運営の“無駄”を見つけ、売上・利益・在庫のバランスを最適化するための強力なツールです。
ここでは、飲食店がABC分析を導入することで得られる3つの大きなメリットを紹介します。
① 売れ筋・死に筋メニューを明確化できる
ABC分析の最大の魅力は、人気メニューと不人気メニューを“感覚ではなくデータで”判断できることです。
たとえば、「お客さんによく出る」と思っていたメニューが、実際の売上データでは全体の5%しか占めていなかった――というのはよくある話です。
逆に、あまり注目していなかったサイドメニューがBランク入りしていた、なんてこともあります。
このように、データで裏付けを取ることで「残すべき」「改良すべき」「やめるべき」の判断が客観的になります。
また、スタッフ間での認識共有にも役立ち、「どの商品を推すべきか」が明確になるため、接客・販促の一貫性も生まれます。
② 原価・粗利率のバランス最適化が可能
ABC分析は、売上と原価のバランスを見直すきっかけにもなります。
売上が高くても原価率が高ければ、利益は薄くなります。
逆に、販売数は少なくても粗利率が高いメニューは、店舗全体の利益を支える“隠れAランク”かもしれません。
粗利率(=(売価−原価)÷売価)を併せて分析すれば、
- 「売上は高いが利益が薄い」メニュー → 価格調整や仕入れ見直し
- 「売上は少ないが利益が厚い」メニュー → 販促・セット提案で販売数を増やす
といった戦略的判断が可能です。
さらに、ABC分析をFLR比率(Food・Labor・Rent=原価・人件費・家賃)と照らし合わせることで、より実践的な利益構造の把握ができます。
たとえば、Aランク商品の調理に人件費が多くかかるなら、オペレーション改善でFLRのバランスを取る――このように、店舗全体の「効率性」まで分析できるのが強みです。
③ 在庫・仕入れ・廃棄ロスを改善できる
ABC分析を導入すると、仕入れや在庫管理の精度が格段に上がります。
Aランク商品に使う食材は、回転率が高いため多めに発注してもリスクが少ない。
一方で、Cランク商品の食材は回転が遅く、廃棄ロスを生む原因になりがちです。
分析結果をもとに仕入れ量を調整するだけで、
- 食材ロスの削減
- 仕入れコストの最適化
- 冷蔵庫・倉庫スペースの有効活用
といった効果が期待できます。
また、在庫削減はキャッシュフロー改善にも直結します。
無駄な仕入れを抑えることで、運転資金に余裕が生まれ、次の投資(メニュー開発や販促)に回せる――これもABC分析の“見えない効果”のひとつです。
まとめると、ABC分析の3つのメリットは以下の通りです。
| メリット | 期待できる効果 |
|---|---|
| 売れ筋・死に筋の可視化 | メニュー構成の最適化・販促強化 |
| 原価・粗利率の最適化 | 利益率改善・FLRバランス向上 |
| 在庫・仕入れの改善 | ロス削減・キャッシュフロー改善 |
感覚に頼らない“数字の経営”を実践するための第一歩が、ABC分析です。
ABC分析のやり方|Excel・POSデータを使った実践手順
ABC分析は、特別なツールがなくても始められる“最もシンプルなデータ分析”です。
必要なのは、売上と原価のデータ、そしてExcelやGoogleスプレッドシートだけ。
ここでは、初心者でも今日から実践できるステップを3段階で解説します。
STEP1 売上・粗利データを抽出する
まずは分析に使うデータを集めましょう。
期間は「1か月」または「3か月」など、季節変動を加味しつつ一定期間を設定します。
POSレジや会計システムから、次の項目をエクスポートします。
- 商品名(メニュー名)
- 販売数量
- 売上金額
- 原価
- 粗利額(=売上−原価)
もしPOSを使っていない場合は、日報や手書きの伝票をもとに集計しても構いません。
小規模店舗であれば、週単位・月単位のざっくりしたデータでも十分です。
ここで大切なのは、「売上額」だけでなく粗利額も必ず出すこと。
これが後の「本当に儲かるメニュー」を判断する決め手になります。
STEP2 構成比・累積比を算出する
データが揃ったら、Excelやスプレッドシートに次のような表を作成します。
| メニュー | 売上金額 | 構成比(%) | 累積構成比(%) | ランク |
|---|---|---|---|---|
| コーヒー | 120,000円 | 30.0 | 30.0 | A |
| カフェラテ | 100,000円 | 25.0 | 55.0 | A |
| ティー | 70,000円 | 17.5 | 72.5 | B |
| ケーキ | 50,000円 | 12.5 | 85.0 | B |
| スムージー | 30,000円 | 7.5 | 92.5 | C |
| サンドイッチ | 20,000円 | 5.0 | 97.5 | C |
- 各商品の売上を全体売上で割り、構成比を求めます。
- 売上の高い順に並べ、構成比を上から累積して合計します。
- 累積構成比が「上位70%=A」「次の20%=B」「残り10%=C」となるように分類します。
このとき、売上ではなく粗利額を基準にした表も同時に作成すると、より精度が高まります。
売上ベースと粗利ベースの結果を比較すれば、
「売れているけど儲からない商品」や「売上は少ないけど利益貢献が大きい商品」が一目で分かります。
STEP3 ランクごとに改善アクションを設定する
分類が終わったら、いよいよ分析の“本番”です。
ABCランクに応じて、経営判断や販促施策を設計していきましょう。
| ランク | 特徴 | 改善アクション |
|---|---|---|
| Aランク | 店舗の利益を支える主力商品 | 品質維持、安定供給、原材料確保。メニュー上部や看板での露出を強化。 |
| Bランク | 伸びしろのある中堅商品 | 販促キャンペーンやセット販売で販売数アップ。価格調整も検討。 |
| Cランク | 売上・利益貢献の低い商品 | 廃止、改良、季節限定化を検討。無駄な仕入れを削減。 |
たとえば、カフェでスムージーがCランクだった場合、
- 原価が高い食材(フルーツ類)の仕入れを減らす
- 季節限定メニューにして需要期だけ販売する といった形で運用コストを最適化できます。
また、Bランクの商品は「少しの工夫でAランクになりうる宝」。
POPの位置、スタッフのおすすめトーク、SNSでの訴求など、販促施策を加えるだけで売上が一気に伸びることもあります。
業態別に見るABC分析の活用例
ABC分析の本質は「数字でメニューの優先順位を決めること」ですが、業態によって注目すべき指標や改善の方向性は変わります。
ここでは、カフェ・居酒屋・レストランという3つの代表的業態に分けて、具体的な活用事例を紹介します。
カフェ業態|ドリンクとフードの構成を分けて分析
カフェでは、ドリンクとフードを一緒に分析すると傾向が見えづらくなります。
そのため、カテゴリー別(ドリンク/フード/スイーツ)に分けてABC分析を行うのが効果的です。
たとえば、次のような結果になったとします。
| カテゴリー | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|
| ドリンク | ハンドドリップコーヒー、カフェラテ | アイスティー | スムージー |
| フード | トーストセット | サンドイッチ | キッシュ |
| スイーツ | チーズケーキ | ガトーショコラ | 季節限定パフェ |
この結果から見えてくるのは、「スイーツやスムージーの在庫ロスが多く、利益を圧迫している」という現実。
そこで、スムージーは期間限定販売に切り替え、チーズケーキなどの人気スイーツに注力することで、粗利率と回転率の両方を改善できます。
また、BランクのサンドイッチをAランクに引き上げるには、ランチタイムのセット化やドリンク割引キャンペーンなど、販売機会を広げる工夫が有効です。
居酒屋業態|フード×ドリンク別に分類して販促に活用
居酒屋では、ドリンクとフードの構成が多彩で、メニュー数も多いのが特徴です。
そのため、フードとドリンクを分けて分析することで、売上の偏りや在庫ロスを防ぐことができます。
たとえば、以下のような分析結果が出たとします。
| 分類 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|
| フード | 唐揚げ、ポテトフライ、枝豆 | 出汁巻き卵、焼き魚 | デザート、揚げナス |
| ドリンク | 生ビール、ハイボール | サワー各種 | カクテル類、焼酎ボトル |
この結果をもとに、Aランク商品を「推しメニュー」としてPOP強化したり、Bランクのサワー類をAに昇格させるための飲み放題プランを導入するなど、明確な販促戦略を立てることができます。
一方で、Cランクの「焼酎ボトル」や「デザート類」は、在庫や原価を見直すタイミング。
売れ行きの悪いボトルは仕入れを減らし、回転率を上げることでキャッシュフローを改善することができます。
レストラン業態|コース料理・アラカルト別に分析
レストランでは、コース料理とアラカルトの両方を扱う場合が多く、提供時間・食材ロス・調理コストといった多面的な視点が必要です。
たとえば、アラカルトメニューでABC分析を行うと、
- Aランク:ステーキ・パスタ
- Bランク:サラダ・スープ
- Cランク:魚料理・デザート
といった結果が出たとします。
この場合、ステーキやパスタはオペレーション効率を重視して調理フローを改善。
Cランクの魚料理は仕入れ頻度を下げ、季節限定メニューとして提供することでロス削減と新鮮度の両立が可能になります。
また、コース料理では、構成内の各料理の粗利構成比を出すことで、価格設定や食材バランスの見直しができます。
たとえば、前菜のコストが高すぎる場合は、サラダを簡略化してメイン料理に原価を寄せるなど、全体最適の視点で再設計することができます。
ABC分析の“落とし穴”と注意点
ABC分析は非常に有効な経営ツールですが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。
数字の見方を間違えれば、せっかくのデータが“判断ミス”を助長してしまうからです。
ここでは、実際の現場でありがちな3つの落とし穴を紹介します。
データ期間の取り方を誤ると結果が歪む
最も多いミスが、「分析期間を適切に設定していない」ケースです。
ABC分析はあくまで“期間内の売上構成”をもとにランク付けするため、期間が偏ると結果も偏ってしまいます。
たとえば、
- 夏に分析 → アイスドリンクがAランク、ホットドリンクがCランク
- 冬に分析 → 逆にホットがAランク、アイスがCランク
というように、季節要因が反映されすぎる場合があります。
このような偏りを防ぐには、年間や四半期単位など、複数期間のデータを比較するのがポイントです。
また、イベントやキャンペーン期間中のデータを含める場合は、通常月と分けて分析するとより正確な傾向が見えます。
売上依存の盲点|“人気=利益”ではない
「売れている=儲かっている」と思い込むのは危険です。
ABC分析を売上金額だけで判断すると、真の利益貢献を見誤ることがあります。
たとえば、
- Aランクに入ったが、原価率が60%以上で粗利が薄いメニュー
- Cランクに見えるが、原価率20%で利益が厚いメニュー
このようなギャップは珍しくありません。
つまり、“売上ベースのAランク”と“粗利ベースのAランク”は別物なのです。
本当に経営を強くするには、「売上 × 粗利 × 在庫回転率」という3軸で見ることが大切です。
単に人気メニューを増やすのではなく、「どのメニューが最も効率よく利益を生み出しているか」を見抜く視点が求められます。
分析後の放置が最大の失敗
もう一つの落とし穴は、「分析しただけで満足してしまう」ことです。
ABC分析は、定期的な更新と改善サイクル(PDCA)を回してこそ意味があります。
メニューの人気や原価は常に変化します。
季節、仕入れ価格、顧客層、競合の動きによって、A・B・Cの構成は数か月で変わってしまうこともあります。
理想的なのは、月次または四半期ごとに見直す運用です。
定期的に分析を行い、
- BランクがAに昇格した理由
- Cランクに落ちた商品の背景 を確認することで、より正確な経営判断が可能になります。
また、数値だけに頼らず、現場の声やお客様の反応を合わせて判断することも忘れないようにしましょう。
「数字+現場感覚」で見ることで、より立体的で実践的なABC分析になります。
ABC分析を効率化するツール・テンプレート紹介
「分析したいけど、表計算は苦手…」「データをまとめる時間がない」
そんな方でも心配はいりません。
いまは、無料テンプレートやPOSレジの自動分析機能を使えば、誰でもかんたんにABC分析を行えます。
ここでは、現場で本当に使える3つの方法を紹介します。
無料テンプレート(Excel/スプレッドシート)
まずおすすめなのが、ExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートを使う方法です。
「ABC分析 飲食店 テンプレート」などで検索すると、無料でダウンロードできるフォーマットが多数公開されています。
基本構造はシンプルで、
- 商品名
- 売上金額
- 原価
- 粗利額
- 売上構成比/累積構成比 を入力すれば、自動でA・B・Cランクが算出される仕組みです。
自社仕様に合わせて次のようなカスタマイズを加えると、より実務的になります。
- 「カテゴリー列(ドリンク/フード)」を追加
- 「販売日数」「在庫回転率」などの補助指標を追加
- 条件付き書式でAランクを自動色分け
分析初心者でも扱いやすく、“見える化”を始める第一歩として最適です。
POS・クラウド会計の自動分析機能
近年のPOSレジには、ABC分析を自動で行う機能が標準搭載されているものが増えています。
代表的な例としては、
- スマレジ:商品別の売上構成比や粗利率を自動集計。期間比較レポートも充実。
- Airレジ(リクルート):時間帯別・曜日別の売れ筋分析に強く、飲食店の回転率改善にも活用できる。
- ユビレジ:グラフ形式での売上推移・商品別売上を自動可視化。店舗別集計や在庫連携機能も備え、多店舗運営に強い。
こうしたPOSレジを活用すれば、集計作業の時間を大幅に削減でき、スタッフでも簡単に分析結果を共有できます。
さらに、会計ソフト(例:マネーフォワード クラウド会計、freee会計)と連携することで、店舗別・カテゴリー別の収益構造分析も可能になります。
AI分析ツールの活用(中〜大規模店舗向け)
複数店舗を展開している場合や、より精密な分析を行いたい場合は、AI分析ツールやBI(ビジネス・インテリジェンス)ツールの導入を検討してみましょう。
代表的なツールには、
- Tableau(タブロー):売上や粗利データを自動で可視化し、リアルタイムで分析。
- Google Looker Studio:無料で使えるBIツール。POSやスプレッドシートと連携してダッシュボード作成が可能。
- DataSpider Servista:POSや会計データを統合し、AIがパターンを自動抽出。
これらを使えば、「曜日・時間帯・カテゴリーごとに最も利益を生む要素」を自動で可視化できます。
ただし、導入コストや初期設定の工数がかかるため、1〜3店舗規模ならPOS+Excelで十分です。
明日から使える!ABC分析の改善アクション3選
ここまででABC分析の基本から手順までを学びましたが、重要なのは「分析結果をどう活かすか」です。
データを見ただけで満足してしまうのはもったいない。
ここでは、明日からすぐに実践できる3つの改善アクションを紹介します。
どれも、飲食店経営の現場で“即効性”のある取り組みです。
1. Cランクの高原価メニューを削る(ロス削減・原価率改善)
Cランク商品は、売上も利益貢献も少ないメニュー。
中でも注意すべきは「原価が高く、ほとんど注文されない」メニューです。
たとえば、原価率50%以上の食材を使う限定メニューが月に数回しか出ない場合、
その食材は在庫として残り、結果的に廃棄ロスへつながります。
思い切って削除、もしくは季節限定メニュー化して販売期間を短縮しましょう。
これだけでも原価率が1〜3%下がり、月間利益が数万円単位で改善するケースも珍しくありません。
もしメニュー削除に抵抗がある場合は、「Cランクだけど原価が安い」メニューを残し、「高原価Cランク」から削除するという順番で見直すのがおすすめです。
2. Bランク商品の販促POP強化(A昇格を狙う)
Bランクの商品は、伸びしろの塊です。
少しの工夫でAランクに昇格し、売上・利益の柱になる可能性があります。
具体的なアクションとしては、
- メニュー表や看板で「人気急上昇」「おすすめ!」などと訴求
- スタッフのおすすめトークで積極的に紹介
- SNSでBランク商品の写真を発信(限定感を出す)
- セット販売・ドリンクペアリングで露出を増やす
たとえば、あるカフェでは「Bランクのシナモンラテ」を“冬限定の看板商品”として推したところ、販売数が1.8倍に増加。
結果、Aランクへ昇格し、客単価も上昇しました。
販促はコストをかけなくても十分可能。
POPのデザインやスタッフ教育など、“小さな改善の積み重ね”が利益を押し上げます。
3. Aランク商品の安定供給体制を構築(売上維持・満足度向上)
Aランク商品は、店舗の収益を支える“心臓部”です。
そのため、品質と供給を絶対に途切れさせない体制づくりが重要です。
よくある失敗は、「人気メニューが売り切れる」こと。
売れ筋商品を切らしてしまうと、
- 機会損失による売上ダウン
- お客様の満足度・信頼度の低下 につながります。
対策としては、
- 使用食材の在庫を常に可視化し、Aランク食材の仕入れ優先順位を上げる
- 調理マニュアルの標準化で、スタッフ間の品質ブレを防止
- 売上推移をもとに、週次で仕込み量を調整
こうした「Aランクの安定供給=利益の安定化」こそが、ABC分析の最終目的です。
人気メニューを切らさないだけで、リピーターの定着率が上がることも多いのです。
まとめ|ABC分析は「数字で語る経営」の第一歩
飲食店経営において、勘と経験はもちろん大切です。
しかし、感覚だけに頼る経営では、時代の変化やコスト上昇に対応しきれません。
そんな中で、ABC分析は数字で店舗の現状を“見える化”し、判断を明確にする最もシンプルな武器です。
売上・原価・粗利を基準にメニューを3ランクに分類するだけで、
- どの商品が本当に利益を生んでいるのか
- どこにムダが潜んでいるのか
- どのメニューを伸ばすべきか が一目で分かります。
さらに本記事で紹介したように、粗利ベースでの分析やFLR比率(原価・人件費・家賃)との組み合わせ、ツール活用によって、
単なる数字の整理から「利益構造を理解し、意思決定を変える経営ツール」へと進化します。
ABC分析は、店舗規模や業態を問わず実践可能です。
ExcelでもPOSレジでも、まずは一度データを集め、分析してみましょう。
「数字で語れる店長」は、現場を動かす力を持っています。
感覚経営からデータ経営へ。
今日からあなたの店でも、数字で未来を描く経営を始めてみませんか?