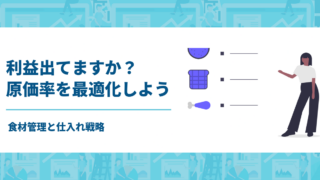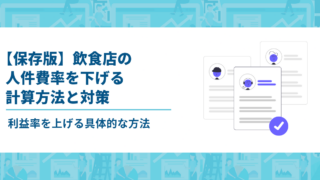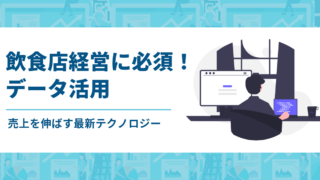「売上は伸びているのに、なぜか利益が残らない」。
多くの飲食店が抱えるこの違和感の正体は、原価・人件費・家賃という“3大コスト”のバランス崩壊にあります。
食材高騰、人手不足による時給上昇、都市部の家賃高止まり――環境は待ってくれません。
だからこそ、FLR比率(Food/Labor/Rent)を正しく理解し、数値で現状をつかむことが、黒字化への最短ルートです。
本記事では、実店舗の運営データと業界統計をもとに、
- 理想の目安
- 計算方法
- 業態別の考え方
- 今日から着手できる改善策
までを丁寧に解説します。
感覚ではなく“見える化”。
まずはあなたの店の健康診断から始めましょう。
FLR比率とは?|飲食店経営の“健康診断”となる指標
FLR比率の基本構造と意味
飲食店経営を数字で読み解くうえで、最も重要な指標のひとつが「FLR比率」です。
これは F=Food(原価)/L=Labor(人件費)/R=Rent(家賃) の3つの頭文字をとったもので、「売上100円のうち、どれだけを主要コストが占めているか」 を示します。
例えば、月商300万円の店舗で原価が90万円、人件費が75万円、家賃が30万円の場合、合計195万円が“主要コスト”です。つまり、売上の約65%を占めているということ。
この65%という数字が、そのお店の「FLR比率」です。
この数値を定期的に追うことで、
「うちは原価に偏っているのか」「人件費が膨らんでいるのか」
といった経営の歪みを“感覚”ではなく“データ”で把握できます。
FLR比率は、いわば飲食店の健康診断表。
数字の変化を読み取れば、経営の良し悪しが一目でわかります。
FLR比率の計算式と具体例
計算方法は非常にシンプルです。
FLR比率 = (原価+人件費+家賃) ÷ 売上 × 100たとえば以下のケースを見てみましょう。
- 売上:300万円
- 原価:90万円
- 人件費:75万円
- 家賃:30万円
この場合、
(90 + 75 + 30) ÷ 300 × 100 = 65%
つまり、売上のうち65%が原価・人件費・家賃で消えており、残りの35%が光熱費や広告費、利益などに充てられるということです。
理想的なFLR比率は後述しますが、この“65%前後”という数字が、黒字店舗の多くに共通する目安ラインです。
記事内では円グラフなどで構成を可視化するのもおすすめです。
視覚的に「どのコストが重いのか」を理解することで、改善の方向性が見えてきます。
FLRとFLの違い(Rを含める意味)
飲食業界では、FL比率(原価+人件費) という指標もよく使われます。
しかし、ここに「R(家賃)」を含めるかどうかで、分析の精度が大きく変わります。
FL比率は“日々の営業効率”を把握するには適していますが、店舗経営全体の採算性を判断するには、R(家賃)を含めたFLR比率が必須です。
なぜなら、家賃は一度契約すると簡単に削減できない固定費。
たとえ人件費を抑えても、家賃が高ければ利益は残りにくい構造になります。
つまり、FLR比率をチェックすることは、「変動費+固定費の両面から経営を見直す」ということ。
店舗の“真の収益力”を測るには、Rを含めた視点が欠かせません。
FLR比率の理想値と“業態別の最適バランス”
飲食店全体での目安:60〜70%が理想
多くの専門家や経営データが示す通り、FLR比率の理想値は60〜70%がひとつの目安です。
この範囲に収まっている店舗は、一般的に「健全な経営バランス」を保っているといえます。
なぜなら、残りの30〜40%で光熱費・広告費・雑費・営業利益をまかなえるからです。
FLRが70%を超えてしまうと、利益率が急激に圧迫され、わずかな売上減や仕入れ価格の変動でも赤字に転落しやすくなります。
逆にFLR比率が低すぎる場合も要注意です。
人件費を削りすぎてサービス品質が下がったり、原価を抑えすぎて料理の満足度が落ちたりすれば、リピート率の低下につながります。
つまり、FLR比率は低ければ良いというものではなく、業態に合った“適正値”を維持することが重要なのです。
【業態別比較表】FLR比率の目安と理由
以下の表は、F&B Sceneが複数の業界調査(中小企業庁「小規模事業者白書」など)を参考に作成した、業態別のFLR比率目安です。
| 業態 | 原価率 | 人件費率 | 家賃率 | FLR合計 | なぜこの水準なのか |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 25% | 25% | 10% | 約60% | 回転率が高く、ドリンク中心で食材コストが低い。効率重視の設計。 |
| 居酒屋 | 35% | 30% | 10% | 約75% | 仕込みや接客に人手がかかり、食材コストも高めだが客単価でカバー。 |
| レストラン | 30% | 30% | 10〜15% | 約70〜75% | サービス性が高く、スタッフと店舗面積が増える分固定費も上昇。 |
| テイクアウト専門 | 25% | 20% | 5% | 約50% | スタッフが少なく、立地コストも抑えやすいため低FLR構造。 |
この表からも分かるように、
「FLR比率=業態に合わせたバランス設計」が大切です。
同じ“飲食店”でも、
- カフェは効率重視でFLRが低い
- 居酒屋やレストランはサービス性重視でFLRが高い といったように、コンセプトによって理想値は変わります。
立地・規模別に見るFLRの違い
FLR比率は業態だけでなく、「立地」や「店舗規模」にも左右されます。
たとえば、駅前や繁華街にある店舗は家賃率が高くなりやすいですが、その分、回転率や客単価でバランスを取る戦略が必要です。
一方で、郊外・住宅地型店舗は家賃が低い代わりに、人件費や仕入れコストの管理が経営を左右します。
つまり、
- 都心型店舗:高家賃を回転率で吸収するモデル
- 郊外型店舗:低家賃を強みに、原価と人件費の最適化で利益を伸ばすモデル
というように、立地条件によって最適なFLRバランスは異なります。
出店時には「家賃率10%以内」を基本に、売上予測とコスト構造を事前にシミュレーションすることが大切です。
FLR比率が高いと何が起きる?|利益構造が崩れる3つのリスク
① 利益圧迫とキャッシュ不足
FLR比率が70%を超えると、店舗経営は一気に不安定になります。
なぜなら、売上の大部分を原価・人件費・家賃で消費してしまうため、利益を確保する余力がほとんど残らないからです。
たとえば月商100万円の小規模店舗で、FLR比率が75%だとします。
残る25万円の中から、光熱費・広告費・消耗品費・雑費を支払えば、手元に残るのは10万円程度。
売上が5%減っただけでも赤字に転落する可能性があります。
しかも飲食業は、売上が毎月一定ではありません。
季節・天候・イベントなどの要因で上下が激しい業界です。
固定的にかかる人件費や家賃を抱えたままでは、少しの売上変動が命取りになるのです。
そのため、経営者は常に「FLR比率=損益分岐点を左右する重要数値」として意識する必要があります。
② コスト連動型リスク(原価・人件費・家賃の連鎖)
FLR比率の怖いところは、一つのコスト上昇が他のコストにも波及する連鎖構造にあります。
たとえば、食材原価が10%上昇したとしましょう。
それを補うためにメニュー単価を上げると、客数が減り、回転率が落ちます。
すると売上に対する人件費比率が上がり、結果としてFLR比率がさらに悪化してしまう――という悪循環に陥るのです。
また、物価上昇や最低賃金の引き上げで人件費が自動的に増える一方、家賃は契約上、簡単に下げられません。
つまり、「原価→人件費→家賃」という順で、雪だるま式に比率が悪化していくリスクがあるのです。
この連鎖を断ち切るためには、定期的にFLR比率を見直し、“どの要素が最も利益を圧迫しているのか”を明確にする必要があります。
③ 投資判断の誤り
FLR比率は、既存店舗の経営分析だけでなく、新規出店や設備投資の判断指標としても非常に重要です。
たとえば、家賃の高い一等地に出店する場合、見込み売上が十分でなければ、初期投資の回収が極端に遅くなります。
出店前に「FLR比率が70%を超えそう」とわかっていれば、立地の再検討や、面積を縮小するなどの判断が可能です。
しかし、数字を意識せずに“感覚”で決めてしまうと、オープン後に「想定より利益が出ない」「人件費がかさむ」といった失敗に直結します。
FLR比率は、単なる経営管理指標ではなく、“投資判断の羅針盤”でもあります。
出店、改装、人員増強――あらゆる経営判断の前に、「FLR比率はいくらになるか?」を試算する習慣を持つことが、成功への第一歩です。
FLR比率を改善する3つの戦略【実践ステップ付き】
① 原価率の最適化:仕入れ・メニュー設計で差をつける
FLR比率を改善するうえで、まず取り組みやすいのが「原価率の見直し」です。
ただし、単純に安い食材へ切り替えるのではなく、“売れる商品構成”を再設計することが重要です。
まず実践すべきは、ABC分析によるメニューごとの利益貢献度の可視化。
売上に占める割合と原価率の両方を整理することで、「高原価なのに売上貢献が低いメニュー」や「利益率が高い人気商品」を明確にできます。
次に取り組みたいのがロス管理の徹底。
食材廃棄は、実質的な“見えないコスト”。
日次の仕込み量をPOSデータと照合し、販売予測精度を高めることで、廃棄を5〜10%減らすだけでも利益率は大きく変わります。
【事例】
都内のあるカフェでは、季節ごとに売上データをもとにメニューを再設計。
原価率を38%→31%に改善しながら、人気商品数を絞り込み、客単価は+80円、利益率は+6pt向上しました。
“コスト削減”ではなく“設計改善”。
これが、原価率を下げても満足度を落とさない唯一の方法です。
② 人件費率の改善:シフト×生産性の最適バランス
人件費は「削る」のではなく、「最適化する」発想が大切です。
まず行うべきは、ピークタイムとアイドルタイムの人員配置データ化。
時間帯別の売上データとスタッフ稼働を照らし合わせ、“どの時間に何人いれば最も効率が良いか”を明確にしましょう。
最近では、クラウド型のシフト管理ツールが強い味方になります。
これらのツールを使えば、「必要な時間に必要な人数だけ働く」仕組みが構築できます。
また、スタッフ教育でマルチタスク化を進めるのも効果的。
ホールとドリンク、キッチンと会計など、複数業務をこなせる体制を整えることで、少人数でも高いパフォーマンスを維持できます。
単純な“人件費カット”ではなく、“生産性最大化”によるFLR改善を目指しましょう。
③ 家賃率の改善:立地再設計と固定費マネジメント
家賃は、FLR比率の中でも最も“動かしにくい”固定費です。
だからこそ、戦略的な見直しと交渉力が鍵になります。
まず、基本指標として覚えておくべきは
「家賃=売上の10%以内」。
これを超えると、利益確保が一気に難しくなります。
改善のアプローチは3段階あります。
- 家賃交渉を検討する 契約更新時には、近隣の相場を調べたうえで家賃交渉を。 賃貸契約でも、長期入居実績があれば値下げ交渉の余地はあります。
- 営業時間の再設計 売上の少ない時間帯を短縮し、光熱費と人件費を削減。 実質的な“坪効率”を高めることが可能です。
- スペースの有効活用 間貸し・ポップアップ・サブスクイベントなど、空き時間や空間を収益化。 家賃を「支出」から「投資」に変える発想が重要です。
立地はブランド価値にも直結しますが、過剰な固定費は経営を縛ります。
FLR比率をもとに、「家賃を払える売上構造」を冷静に設計しましょう。
FLR比率を活用した「成功店舗の実例」
ケース①:原価を下げずにFLR改善に成功したカフェ
東京・中目黒にあるカフェAでは、オープン当初、原価率が38%と高止まりしていました。
人気メニューが多かった一方で、食材のロスや発注過多が原因で、FLR比率は72%に達していたのです。
同店は、「原価を下げる」のではなく「売れるメニューを増やす」という逆転の発想で改革に挑みました。
具体的には、
- 売上データから“注文率の高いドリンクと相性の良いフード”を分析
- 組み合わせ販売(セットメニュー)を導入
- 仕込みロスが多いメニューを一時停止
その結果、原価率は38%→31%に改善。
平均客単価は+100円、FLR比率は65%まで低下しました。
食材の質を落とさず、メニュー構成を最適化することで“体感品質を維持したまま利益を伸ばす”好例です。
ケース②:人件費構造を改革した居酒屋
大阪市内で複数店舗を展開する居酒屋Bは、長年の課題が「人件費の高止まり」でした。
シフト作成を店長の感覚で行っており、繁忙日と閑散日の人員差が激しかったのです。
そこで導入したのが、シフト最適化ツール「シフオプ」。
POSデータと連携し、時間帯別の売上をもとにAIが自動でシフトを提案。
さらに、マルチタスク教育を導入し、ホールとキッチンの垣根を減らしました。
結果、平均稼働時間は1人あたり月8時間削減、人件費率は33%→27%へ改善。
FLR比率は75%から63%へ下がり、営業利益率は+5ポイント上昇しました。
ツール導入費用は約2ヶ月で回収。
“感覚管理”から“データ管理”に変えたことで、継続的な利益体質を実現しました。
ケース③:家賃負担を見直したレストラン
都内中心部に位置するレストランCは、家賃が売上の15%を超えていました。
「立地がブランド」と考え、高額家賃を維持していたものの、コロナ禍以降は稼働率が低下し、赤字転落。
経営チームは思い切って面積を2/3に縮小し、同エリア内での再出店を決断。
厨房をコンパクト化し、内装もミニマルデザインへ変更。
結果、家賃は年間600万円削減。
それでも既存顧客の8割が継続来店し、FLR比率は70%→58%に改善。
同時に利益率は2倍に伸びました。
固定費削減を「ブランド低下」と捉えず、“経営のリストラクチャリング”として再設計した好例です。
これら3つの成功例に共通しているのは、「感覚ではなく数値を基準に経営判断をした」こと。
FLR比率は、“気づきを与えるデータ”として、どの業態にも応用できる強力なツールです。
FLR比率を継続的にモニタリングする仕組みづくり
毎月のPL(損益計算書)でチェックすべき指標
FLR比率の改善は、一度きりの分析で終わりではありません。
「毎月の数字を確認し、変化を追うこと」が、黒字経営を持続させるための鍵です。
チェックすべきは、次の3つの指標です。
- FLR比率(原価+人件費+家賃) → 60〜70%の範囲に収まっているか確認。
- 営業利益率 → 売上に対して最終的に何%の利益が残っているか。 (理想は10%以上)
- 損益分岐点売上 → 利益ゼロになる売上水準を算出し、「安全余裕率」を把握。
この3つを月次PLでモニタリングすることで、
「今月は人件費が膨らみすぎていないか」
「家賃比率が上がっていないか」
など、問題を早期に察知できます。
特に飲食店では、繁忙期と閑散期の差が大きいため、季節ごとのFLR比率の変動も記録しておくと、翌年の計画立案にも役立ちます。
活用ツールとデータ連携術
手動のエクセル管理でも可能ですが、最近ではクラウド型ツールを活用してリアルタイムで数値を見える化する店舗が増えています。
- freee会計/マネーフォワードクラウド会計 → 売上・仕入れ・人件費を自動集計し、月次PLを即時出力。
- POS連携(スマレジ、Squareなど) → 販売データを自動で取り込み、時間帯別・商品別の原価比率を算出可能。
- Airシフト/シフオプ → 勤怠・給与情報を統合し、人件費率を日単位で可視化。
これらを組み合わせることで、“見える化経営”が実現します。
経営者は、毎朝ダッシュボードを見るだけで店舗の健康状態を把握できる――
そんな仕組みを作ることが理想です。
【テンプレート付き】FLR管理表の作り方
手軽に始めたい場合は、以下のような簡易フォーマットを使うのがおすすめです。
| 月 | 売上高 | 原価 | 人件費 | 家賃 | FLR比率 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,000,000 | 900,000 | 750,000 | 300,000 | 65% | 12% |
| 2月 | 2,800,000 | 850,000 | 720,000 | 300,000 | 67% | 8% |
このように、月ごとの数値を一覧化すれば、「どの月にどのコストが重いか」が一目瞭然です。
さらに、前年比や前年同月比を入れることで、改善効果の可視化が可能になります。
F&B Sceneでは、この管理表テンプレートをもとに、自社の複数店舗を横断して比較する仕組みを導入しており、経営判断のスピードが大きく向上しました。
経営の数字を「見るだけで終わらせない」。
“分析 → 改善 → 定着”のサイクルを作ることで、FLR比率は初めて意味を持ちます。
まとめ|FLR比率を制する者が飲食店経営を制す
FLR比率は、飲食店経営における「経営の健康診断表」です。
この数字ひとつで、店舗の体質・利益構造・リスク耐性までも見えてきます。
理想は 60〜70%以内。
この範囲をキープできていれば、原価・人件費・家賃のバランスが取れており、
残りの30〜40%を光熱費や利益に振り分けることができます。
しかし、FLR比率が高い店舗は「がんばっているのに利益が出ない」状態になりやすく、感覚ではなく“数値で経営を把握する”習慣が不可欠です。
今日からできるアクションは、次の3つ。
- まずは現状を数値化する 月次PLや管理表を使い、FLRを算出してみる。
- 業態と立地に合った目標値を設定する 業種別目安(カフェ60%/居酒屋75%/レストラン70%)を参考に、自店の理想を決める。
- 改善サイクルを回す 原価・人件費・家賃を見直し、毎月の変化を追う。
利益を出している店舗の多くは、「勘」ではなく「数字」で判断しています。
FLR比率は、経営者が現場と経営をつなぐ“共通言語”。
数字を見れば、打つべき手が自然と見えてきます。
コストを抑えながら、サービス品質も落とさない。
そんな“持続的に強い店”をつくるために、今日からFLR比率をあなたの経営指標に取り入れてみてください。